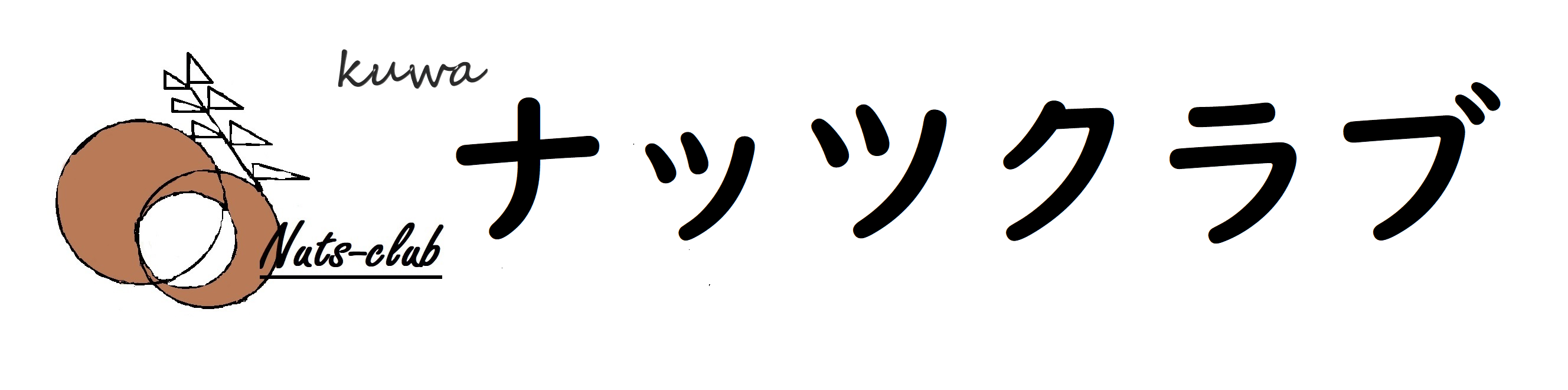序論:伊勢国における双極的聖域の構造
三重県における神道信仰の地図を俯瞰した際、その南端に鎮座する伊勢神宮(伊勢市)と、北端に位置する多度大社(桑名市)は、単なる地理的な対照をなすだけでなく、千三百年以上にわたる深い神学的、歴史的、そして物質的な紐帯によって結ばれている 。伊勢神宮が皇祖神・天照大御神を祀る日本最大の聖域であるのに対し、多度大社はその御子神である天津彦根命を主祭神とし、古来より「北伊勢大神宮」あるいは「伊勢の北門」と称されてきた 。
この両社の関係性は、記紀神話における天照大御神と素戔嗚尊の誓約に端を発する血縁的正当性に基づき、中世の神仏習合期には多度が神道の変革を先導する役割を果たし、近世においては伊勢参宮の完結性を担保する「両参り」の思想へと昇華された 。また、現代に至るまで継続される式年遷宮の資材再利用システムは、伊勢の神聖な中心部から多度の地へと神気が物質的に伝播する循環構造を形成している 。本報告書では、神話、歴史、建築、祭祀、そして現代の文化継承という多角的な視点から、多度大社と伊勢神宮の間に流れる不可分な関係性を学術的・専門的な見地から詳述する。
第一章:神話的起源と系譜学的正当性
天照大御神と天津彦根命の誓約
多度大社と伊勢神宮を繋ぐ最も根源的な絆は、記紀神話における「誓約(うけい)」の場面に求められる 。素戔嗚尊が自身の潔白を証明するために高天原の天照大御神と対峙した際、互いの持ち物を交換して神を産む儀式が行われた 。この時、天照大御神の八坂瓊五百箇御統(やさかにのいおつのみすまる)から生まれた五柱の男神のうち、三番目に誕生したのが多度大社の主祭神である天津彦根命(あまつひこねのみこと)である 。
この誕生の経緯は、天津彦根命が天照大御神の直系の「第三皇子」であることを定義し、多度大社が伊勢神宮と極めて近い血縁関係にあることを宗教的に保証している 。天照大御神を母とし、天津彦根命を子とするこの系譜学的構造は、多度大社が「北伊勢大神宮」という、伊勢神宮の分身的な地位を許される最大の根拠となっている 。
| 誕生順 | 神名 | 伊勢神宮・皇室との関係 | 多度大社・周辺氏族との関係 |
| 第一子 | 天忍穂耳命 | 天皇家の直接の祖神 | 出雲神話・皇統の源流 |
| 第二子 | 天穂日命 | 出雲国造・土師氏の祖神 | 出雲の平定に関与 |
| 第三子 | 天津彦根命 | 天照大御神の第三皇子 | 多度大社の主祭神、桑名首の祖 |
| 第四子 | 活津日子根命 | – | 広域的な信仰圏の形成 |
| 第五子 | 熊野久須毘命 | – | 熊野信仰との関連性 |
孫神・天目一箇命と多度両宮の形成
多度大社の神学的構造をさらに強固にしているのが、別宮・一目連神社(いちもくれんじんじゃ)に祀られる天目一箇命(あめのまひとつのみこと)の存在である 。天目一箇命は天津彦根命の御子神であり、天照大御神から見れば孫神にあたる 。この「親(天照大御神)―子(天津彦根命)―孫(天目一箇命)」という直系三代の神学的ピラミッドが、伊勢神宮と多度大社の間に完成された宗教空間を創出している 。
天目一箇命は製鉄・鍛冶の神として知られ、金属加工に携わる職人集団の祖神としても崇められてきた 。この事実は、多度大社が古代において単なる農耕の神としてだけでなく、工業や軍事の要衝としての性格を帯びていたことを示唆している 。平安時代後期に伊勢平氏が多度大社を「軍神」として信仰した背景には、こうした鉄の神としての性格も関与していたと考えられる 。
第二章:地理的・空間的統合:伊勢の北門としての機能
多度山と伊勢湾の視認的ネットワーク
多度大社が「伊勢の北門」と呼ばれる背景には、古代から中世にかけての海上および陸上の交通路と、伊勢国全体の霊的なゾーニングが深く関係している 。多度大社の背後にそびえる多度山(標高403メートル)は、濃尾平野の西端に位置し、伊勢湾の海上からも容易に視認できるランドマークであった 。
古来、航海者や旅人は、海上から見える多度山の状況から天候を予測し、安全な航行を祈願した。この山のふもとに鎮座する多度大社は、美濃国(岐阜県)や尾張国(愛知県)から伊勢国へ入る旅人にとって、最初に遭遇する最高位の聖域であった 。このような地理的条件が、多度大社を伊勢神宮への「序奏」としての地位へと押し上げたのである 。
| 呼称 | 意味 | 歴史的・神学的背景 |
| 北伊勢大神宮 | 伊勢国北部の最高社格 | 主祭神が天照大御神の子神であることによる |
| 伊勢の北門 | 伊勢国への北の入り口 | 七里の渡しを含む交通の要衝に位置する |
| 北伊勢総鎮守 | 地域の守護の要 | 多度五社を統括し、地域全体の平安を司る |
「北向」の神格と伊勢神宮への導き
多度大社と伊勢神宮の関係性を語る上で、多度山の神々が天照大御神を伊勢の地へと導いたという伝承は極めて重要である 。社伝によれば、多度山の神々は、倭姫命(やまとひめのみこと)に随伴して天照大御神を伊勢国へお招きし、その安住の地へと案内したとされる 。
この「案内役」としての役割は、多度大社が伊勢神宮に対して持つ従属的かつ不可欠な補完関係を象徴している。また、多度山の宇賀地区には、伊勢神宮外宮の祭神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)と同じ稲作の神を祀る祠が存在し、南北の神が対をなして日本全土の食糧供給と平安を守護するという、ダイナミックな宗教的ランドスケープを形成している 。
第三章:民俗学的巡礼論と「片参り」の回避
俗謡にみる旅の作法と信仰の完結性
江戸時代、伊勢参宮は庶民にとって最大のレクリエーションであり、かつ神聖な義務であった。この時期に広まった「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片参り」という俗謡は、当時の巡礼者たちの行動指針を明確に示している 。この俗謡に含まれる「片参り」という表現は、単なる不完全さを超えて、親子神のいずれかを欠くことが神に対する不誠実であるという宗教的な戒めを含んでいた 。
この思想の根底には、本源的な力を持つ親神(伊勢神宮)と、その力を地域社会や個人の生活へと具体的に媒介する子神(多度大社)の両方に参拝することで、初めて神の恩寵が全うされるという、日本の神道信仰特有の「両参り」の構造がある 。これは信濃の善光寺と北向観音、あるいは伊勢の内宮と外宮の関係と同様の双極的な信仰の枠組みを、伊勢国全域という広域的なスケールに適用したものである 。
桑名藩の宗教政策と巡礼経済
多度大社の名声と伊勢神宮との紐帯が江戸時代に決定的なものとなったのは、時の権力者による意図的な振興策が功を奏した面も大きい 。元亀2年(1571年)の織田信長による焼き討ちによって、多度大社は社殿も神宝も失うという壊滅的な打撃を受けた 。この危機を救ったのが、桑名藩主・本多忠勝である 。
忠勝は慶長10年(1605年)に多度大社を再建し、莫大な寄進を行うことで、同社を桑名藩の精神的象徴として復活させた 。忠勝の狙いは、伊勢参宮に向かう全国の旅人を桑名に引き留め、多度参拝を標準的なルートとして定着させることで、藩の経済的な繁栄と格付けの向上を図ることにあった 。その後の歴代藩主もこれを継承し、「多度祭御殿」を建立して上げ馬神事を保護するなど、多度大社を「伊勢の北の重要拠点」として維持・強化し続けたのである 。
第四章:神仏習合の先駆的多度と伊勢神道の純粋性
満願禅師と多度神の託宣:パラダイムの転換
多度大社と伊勢神宮の関係を考察する際、日本における「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」の歴史は欠かせない。8世紀の奈良時代、天平宝字7年(763年)、多度大社は日本の宗教史に刻まれる「神の仏教帰依」という衝撃的な事件の舞台となった 。
『多度神宮寺伽藍縁起並資財帳』の記述によれば、多度の神は満願禅師に憑依し、「われは多度の神であるが、長年の罪の報いで神という不自由な身に甘んじている。この苦しみを脱するために仏教に帰依したい」と告げたという 。この託宣は、それまで万能の存在であった日本の神が、自らの業(カルマ)を認め、外来の仏教による救済を求めるという、極めて革新的なパラダイム転換であった 。
| 事象 | 伊勢神宮の立場 | 多度大社の立場 | 宗教史的意義 |
| 神仏習合 | 仏教の排除を徹底し、神道の純粋性を維持 | 神が仏に救いを求める託宣を出し、神宮寺を建立 | 補完的な役割分担の成立 |
| 神階・位階 | 唯一無二、最高位の存在(正一位以上) | 貞観3年に正二位へと累進、二宮として確立 | 国家の公式な序列における安定 |
| 神宮寺の役割 | 神宮寺は後に設けられたが、本体とは一定の距離 | 多度神宮寺が中心的な役割を果たし「多度大菩薩」へ | 神道の進化と適応の実験場 |
役割分担としての「純粋」と「習合」
この多度における神仏習合の成功は、伊勢神宮との対比において極めて重要な役割を果たした。伊勢神宮が皇室の祖神として、また国家の根源的な象徴として、仏教の介入を厳格に拒み続ける「神道の一滴の純粋さ」を守り抜いたのに対し、多度大社はより柔軟に、時代の要請(仏教による国家鎮護や個人の救済)に応える「前衛的な宗教空間」として機能したのである 。
伊勢神宮が「公(おおやけ)」の、不変の権威を象徴する一方で、多度大社は民衆の苦悩や現世利益に寄り添う「私(わたくし)」と「公」の媒介者としての性格を強めた。多度の神が「多度大菩薩」として仏教的な徳を身にまとうことで、伊勢国全体としては「古来の神道の純粋性」と「新しい仏教の救済」を同時に提供できる、調和のとれた宗教システムが完成したといえる 。
第五章:物質的・建築的連続性と「常若」の物質循環
唯一神明造の意匠による神学的証明
多度大社と伊勢神宮の紐帯は、形而上の神話や歴史だけでなく、具体的な建築様式という視覚的な形態を通じても強力に表現されている。多度大社の本宮「多度神社」および別宮「一目連神社」の社殿は、伊勢神宮の正殿にのみ許される「唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)」を模した形式を採用している 。
この建築様式は、弥生時代の穀倉を起源とし、切妻造の茅葺屋根、平入り、そして地中に直接柱を立てる「掘立柱(ほったてばしら)」を特徴とする 。装飾を極限まで排したヒノキの素木造りは、神道の美学である「清浄」と「簡素」を体現している 。多度大社がこの形式を踏襲していることは、同社が伊勢神宮と一体不可分の存在であり、その神聖さを等しく共有する資格を持っていることを視覚的に証明するものである 。
| 建築要素 | 伊勢神宮(内宮・外宮) | 多度大社(本宮) | 共通の象徴的意味 |
| 屋根形式 | 唯一神明造(茅葺・切妻) | 神明造(伊勢の意匠を継承) | 古代の生命力と豊穣の保存 |
| 柱の形式 | 掘立柱(心御柱を中軸とする) | 掘立柱(伝統的工法) | 神霊が地下から昇降する通路 |
| 千木(ちぎ) | 内宮:内削ぎ / 外宮:外削ぎ | 神明造の伝統的な意匠 | 神格の峻別と天への指向 |
| 鰹木(かつおぎ) | 内宮:10本 / 外宮:9本 | 屋根上の鰹木による装飾 | 権威と調和の象徴 |
式年遷宮の古材が紡ぐ物質的リレー
伊勢神宮と多度大社の間に存在する最も驚くべき物理的な関係は、20年に一度の「式年遷宮(しきねんせんぐう)」によって生み出される「古材の循環」である 。遷宮の際、解体された旧社殿の木材は廃棄されることなく、日本各地の神社へとリユース(再利用)されるが、その中でも桑名の地には特別な意味を持つ資材が届けられる 。
伊勢神宮の内宮・宇治橋の両端に立つ大鳥居は、遷宮の度に新調されるが、その役目を終えた旧材は、三重県桑名市の「七里の渡し(しちりのわたし)」の鳥居として移設・再利用されるのが古くからの習わしである 。この移設のプロセスは、伊勢の神気が木材という依代を通じて、物理的に北へと伝播していくダイナミックな流れを形成している 。
- 内宮の正殿: 伊勢神宮の内宮正殿を20年間支えた「棟持柱」が、次の遷宮で宇治橋の大鳥居へと生まれ変わる 。
- 宇治橋の鳥居: 参拝者を迎える宇治橋の鳥居としてさらに20年間、風雨に耐えながら聖域を守護する 。
- 七里の渡しの鳥居: 合計40年の神宮奉仕を終えた木材が、桑名の「伊勢国一の鳥居」として移設され、伊勢路に入る最初の門として機能する 。
このように、多度大社へ向かう街道の起点である桑名の鳥居は、伊勢神宮の最も神聖な中心部を支えていた木材そのものによって構成されている 。旅人は、伊勢に到達するずっと以前に、桑名の地で既に伊勢神宮の物理的な実体に触れることとなるのである。この物質的なリレーこそが、多度大社が伊勢神宮の「北の玄関口」であることを裏付ける最強の証拠といえる 。
第六章:白馬伝説と上げ馬神事の神学的意義
「上げ馬神事」にみる能動的な神威
多度大社のアイデンティティを語る上で欠かせないのが、毎年5月4日・5日に執り行われる「上げ馬神事(多度祭)」である 。この神事は、少年騎手が馬にまたがり、約2メートルの絶壁(上げ坂)を駆け上がるという、勇壮かつ過酷な儀礼である 。この結果によってその年の農作物の作柄を占うという「農耕占肉」の性格を持っており、三重県無形民俗文化財にも指定されている 。
伊勢神宮が執り行う「祈年祭」や「新嘗祭」が、静謐な祈りを通じて国家規模の豊穣を請い願う「静」の祭祀であるならば、多度大社の上げ馬神事は、人間と馬の生命力を限界まで引き出し、物理的な障壁を乗り越えることで神意を問う「動」の祭祀である 。この「静」と「動」のコントラストは、本源的な中心(伊勢)と、それを守護し、具体的現実に適用する周縁(多度)という、両社の機能的な役割分担を象徴している 。
白馬伝説と神の使いとしての役割
多度大社には「白馬(しろうま)伝説」が伝わり、境内には今も生きた白馬が「神馬」として飼育されている 。伝説によれば、この白馬は人々の願いを背に乗せて多度山に登り、神に直接声を届ける使者であるという 。
伊勢神宮においても天皇から奉納された神馬が飼育されているが、多度の白馬は、より参拝者に近い距離で「願いを運ぶ実体」としての存在感を放っている 。参拝者は馬に餌を与え、直接その神気に触れることで、自身の祈りが伊勢の神々へと確実に届けられることを確信する 。このように、馬という象徴を通じて、多度大社は伊勢神宮への祈りをより具体化し、人々の日常へと引き寄せる役割を担っているのである 。
第七章:多度両宮と一目連神社の特殊神格
「一目連」という自然の猛威と救済
多度大社の奥深さを象徴するのが、別宮「一目連神社」である 。その祭神である天目一箇命は、天津彦根命の子神でありながら、伝説においては「片目の竜(龍)」へと変貌し、天候を自在に操る神威を示すとされる 。
一目連神社の社殿には「扉がない」という極めて特異な建築的特徴がある 。これは、龍と化した神がいち早く神域を出て神威を揮うために、自由に出入りできるようにしたためと言い伝えられている 。伊勢湾岸一帯では、一目連の神が活動すると大風(台風や暴風)が吹くと言い伝えられ、古来より畏怖と崇敬の対象となってきた 。
産業の守護神としての多角的側面
天目一箇命は、その神名の通り「片目」であり、これは鍛冶職人が炎を見続けて片目を失明することが多かったことに由来すると考えられている 。このため、同社は鉄工・金属産業の守護神として全国から篤い信仰を集めている 。毎年11月8日に行われる「ふいご祭」には、現代の鉄工関係者も多く参列し、神前に感謝を捧げる 。
伊勢神宮が稲作と太陽(天照大御神)を司る「農の神」を中核とするならば、多度大社はその子孫の神を通じて、製鉄や風雨という「工と自然現象」を司る役割を分担している 。この神学的な多層性は、伊勢国が単なる農業地帯ではなく、古くから鋳物や刃物、そして海運の要衝として栄えてきた歴史的実態を反映しているのである 。
第八章:現代の巡礼:参拝ルートと文化の継承
現代の「両参り」モデルコースの提案
現代においても、伊勢神宮と多度大社を巡る旅は、三重県の精神的ルーツを辿る王道のルートとして推奨されている 。名古屋や大阪といった都市部からのアクセスも良く、桑名から伊勢へと南下する旅程は、地理的にも神話的にも自然な流れを形成する 。
| ステップ | 目的地 | 意義と目的 |
| 1. 導入 | 多度大社 | 「伊勢の北門」にて御子神に挨拶し、身を清める。白馬に祈りを託す |
| 2. 禊 | 二見興玉神社 | 伊勢神宮参拝の前に、夫婦岩の浜にて穢れを落とす「浜参宮」を行う |
| 3. 外宮 | 伊勢神宮 外宮 | 衣食住を司る豊受大御神に、日々の生活の安定を感謝する |
| 4. 内宮 | 伊勢神宮 内宮 | 天照大御神(親神)に国家の安泰と自身の至誠を捧げ、巡礼を完結させる |
このルートは、単なるスタンプラリー的な観光ではなく、神話上の親子の物語を追体験するプロセスである 。多度で始まり、伊勢で終わる旅程は、神の力が北から南へと、あるいは中心へと収束していくエネルギーの流れを体感させるものとなっている 。
授与品と伝統行事の現代化
多度大社は、伝統を重んじながらも、現代の参拝者のニーズに合わせた文化の継承にも積極的である 。馬をモチーフにした「うまくいく絵馬」や「うまくいく守」は、ビジネスや受験などの成功を願う人々から絶大な支持を得ており、これらは伊勢神宮のシンプルな「御札」とは対照的な、多度独自の民俗的な魅力を発信している 。
また、夏の風物詩である「提灯祭り」や、小笠原流による「流鏑馬祭」などは、多度が単なる過去の遺物ではなく、地域社会の活気ある文化拠点であることを証明している 。これらの祭礼は、伊勢神宮の式年遷宮が体現する「時間的な常若」と同じように、多度の地において「空間的な常若」を維持し続けるための不可欠な要素となっているのである 。
第九章:結論:常若の絆が結ぶ未来
伊勢神宮と多度大社の関係を調査・分析した結果、両社は単なる親社と子社という形式的な関係を超えた、日本の神道信仰の根幹を支える「双極の座標系」を形成していることが明らかとなった 。
神話的には、天照大御神という本源的な光から生まれた天津彦根命が多度の地を拓き、歴史的には、伊勢神宮が神道の純粋性を守る一方で多度が神仏習合という新しい救済の道を切り開いた 。建築的には、式年遷宮の古材が伊勢から桑名へと受け継がれる物質的な連鎖が、南北を結ぶ見えない糸となっている 。そして民俗的には、「片参り」を避けるという旅の作法が、千年にわたり人々の心に「両社を併せて敬う」という信仰の型を刻み込んできた 。
伊勢神宮が、日本の伝統の「不変なる中心」であるならば、多度大社は、その中心から発せられる神威を人々の生活の細部へと繋ぎ、時には勇壮な馬の祭事として、時には製鉄の守護として、多様な形で具現化させる「躍動する周縁」である 。この中心と周縁の絶妙なバランスこそが、伊勢国を日本における最も特別な霊域として存続させてきた原動力に他ならない。
今後、さらなる式年遷宮が重ねられ、古材がまた桑名の鳥居を新しくしていくたびに、この絆は強化され、未来へと継承されていくであろう 。伊勢神宮への参拝を志す者は、ぜひ北の入り口である多度大社に足を運び、神話の親子が奏でる壮大な信仰のハーモニーに耳を傾けるべきである。それこそが、日本人の心に受け継がれてきた「清浄」と「躍動」の両輪を体験する、真の参宮の姿であると言えるからである 。