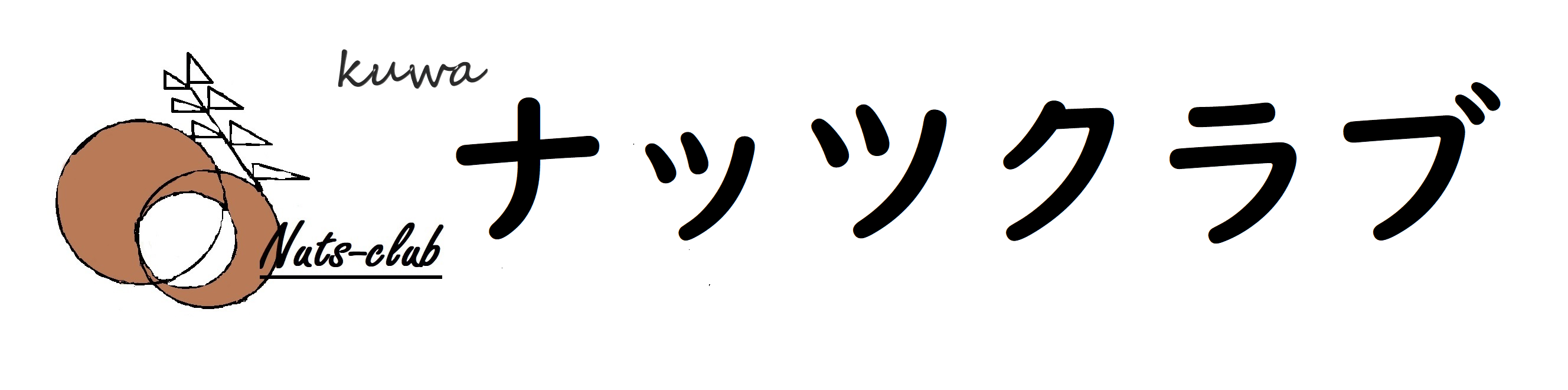1. 導入:日曜午前9時、私たちは「美」という静寂に没入する
日曜日の午前9時。テレビから流れるあのお馴染みの旋律が聞こえてくると、騒々しい日常のノイズがふっと消え、リビングが美術館の回廊へと変貌する――。NHK Eテレが誇る至高の教養番組『日曜美術館』が、2026年、ついに放送開始50周年という金字塔を打ち立てました。半世紀もの間、一貫して「美とは何か」を問い続けてきたこの番組が、その記念すべきアニバーサリーイヤーの特別企画として選んだテーマ、それが**「わたしと熊谷守一2026」**です。なぜ今、私たちは再び熊谷守一という画家に立ち返らなければならないのか。その導入から深く掘り下げていきましょう。
半世紀の重み:なぜ『日曜美術館』は2026年に50周年を迎えられたのか
1976年の放送開始以来、日本のテレビメディアにおいて『日曜美術館』は独自の地位を築いてきました。流行が瞬く間に消費され、情報のスピードだけが過熱する現代において、一つの番組が50年続くというのは奇跡に近い出来事です。その原動力は、徹底した「本物志向」にあります。
単なる展覧会の紹介番組に留まらず、作品の背後にある作家の孤独、時代との葛藤、そして一筆に込められた執念を、極上の映像美で描き出す。2026年という、AIが画像を生成し「美」の定義が揺らぐ時代だからこそ、人間が五感を通じてキャンバスに定着させた「体温のある美」を伝えるこの番組の価値は、かつてないほど高まっています。視聴者は、45分間の放送を通じて、単なる知識ではなく「視る力」を養ってきたのです。
熊谷守一という「再会」:50周年特集のトップバッターに彼が選ばれた必然性
50周年の節目に、番組が「再会」の相手として選んだのが、没後もなお絶大な人気を誇る画家・熊谷守一(1880-1977)です。彼は晩年の30年間、自宅の庭から一歩も外へ出ず、蟻の歩き方や草花の揺れをじっと見つめ続けました。
番組のアーカイブを紐解けば、守一はこれまで何度も特集されてきました。しかし、2026年の今、彼を特集することには特別な意味があります。パンデミックを経て、自分たちの「足元の豊かさ」を見つめ直した現代人にとって、守一の生き方は「究極のミニマリズム」であり、同時に「無限の宇宙」そのものです。番組は、過去の膨大なライブラリー映像を使いながらも、決して懐古主義には陥りません。2026年の視点から、守一のシンプルを極めた線と色彩が、いかに現代の閉塞感を打ち破るパワーを持っているかを証明しようとしているのです。
情報の奔流の中で:現代人が今こそ「守一の眼」を必要とする理由
私たちは今、1日に数千枚もの画像をSNSで消費しています。しかし、その中でどれだけのものを「凝視」できているでしょうか。熊谷守一は、一匹の蟻が歩き出す瞬間の「左の二番目の足」から動き出すという事実を突き止めるために、何時間も地面に這いつくばりました。
今回の特集「わたしと熊谷守一2026」では、現代を代表するデザイナー・皆川明さんが案内人を務めます。皆川さんのような「現代の表現者」が守一の作品と対峙する姿を描くことで、番組は視聴者に問いかけます。「あなたは、自分の目の前にある小さな命を、どれだけの解像度で見つめていますか?」と。 この放送は、単なる美術解説ではありません。情報過多な社会で摩耗した私たちの「感性の解像度」を、再び初期化(リセット)し、豊かに研ぎ澄ますための儀式なのです。日曜の朝、テレビの前に座る45分間は、私たち自身が守一の眼を借りて世界を再定義する、贅沢な瞑想の時間となるはずです。
2. 基本データ:知られざる「日美」の軌跡と放送概要
テレビ番組が50年続く。それは単なる長寿番組という言葉では片付けられない、一つの「文化」の形成を意味します。2026年2月22日に放送される「わたしと熊谷守一2026」は、その半世紀にわたる蓄積が爆発する瞬間です。ここでは、番組の骨格を成す放送データと、その変遷の歴史を紐解いてみましょう。
2026年2月22日、放送決定:45分間に凝縮された「50年」のアーカイブ
今回の特集「わたしと熊谷守一2026」は、2026年2月22日(日)午前9時分から9時45分までの45分間、NHK Eテレにて全国放送されます。この「45分」という枠組みこそが、日美(にちび)の伝統的なリズムです。
特筆すべきは、2026年という年が、1976年に産声を上げた番組にとってちょうど50周年のメモリアルイヤーであることです。今回の放送では、最新の4K・8K超高精細カメラで捉えた守一の肉筆画と、1970年代に16mmフィルムで撮影された貴重な取材映像が、時空を超えて交錯します。デジタルリマスターされた過去の映像には、晩年の守一が庭の土をいじる指の汚れや、愛用の眼鏡に反射する光までが鮮明に蘇っており、視聴者はあたかも50年前の守一の自宅にタイムスリップしたかのような錯覚を覚える構成となっています。
番組ロゴとテーマ曲の変遷:私たちの耳と目に焼き付いた「日曜の音」
『日曜美術館』を語る上で欠かせないのが、視聴者の脳裏に刻まれた五感の記憶です。歴代のテーマ曲は、番組の顔として時代を彩ってきました。 初代テーマ曲から、池辺晋一郎氏、そして近年の現代音楽家による繊細なアンサンブルまで、その音色は常に「日曜の朝の静謐」をデザインしてきました。2026年の特別企画では、これら歴代のテーマ曲がセクションごとに劇伴として使用されるという、ファン垂涎の演出が予定されています。
また、番組のタイトルロゴの変遷も、日本のグラフィックデザイン史そのものです。力強い筆文字の時代から、洗練されたモダンなフォントへと変化しながらも、常に画面中央に凛として佇むその姿は、番組が守り続けてきた「普遍的な美」の象徴です。今回の特集では、熊谷守一が好んで書いた独特の「守一文字」へのオマージュを込めた、特別仕様のアートワークが画面を彩ります。
Eテレが守り抜く「教養」の最後の砦:視聴率を超えた価値の創造
民放の美術番組が縮小・淘汰される中で、なぜ『日曜美術館』だけが、これほどまでの熱狂を維持し続けているのでしょうか。それは、NHK Eテレがこの番組を単なる「情報の伝達」ではなく「公共財としての芸術体験」と位置づけているからです。
1976年の開始当初から、番組は「わかりやすさ」よりも「作品との対話」を優先してきました。ナレーションで全てを説明せず、数秒間の「沈黙」を恐れない編集。作品の細部をじっくりと見せる長いフィックス(固定)ショット。これらの手法は、タイパ(タイムパフォーマンス)が重視される2026年のメディア環境において、極めて贅沢で挑戦的な「スローメディア」の姿勢を貫いています。名古屋放送局をはじめとする各地域の局が連携し、全国各地の美術館と視聴者を結ぶそのネットワークは、日本人の美意識を底上げしてきたといっても過言ではありません。今回の守一特集もまた、視聴率という物差しでは測れない、日本文化の豊かさを証明する放送となるでしょう。
2. 基本データ:知られざる「日美」の軌跡と放送概要
テレビ番組が50年続く。それは単なる長寿番組という言葉では片付けられない、一つの「文化」の形成を意味します。2026年2月22日に放送される「わたしと熊谷守一2026」は、その半世紀にわたる蓄積が爆発する瞬間です。ここでは、番組の骨格を成す放送データと、その変遷の歴史を紐解いてみましょう。
2026年2月22日、放送決定:45分間に凝縮された「50年」のアーカイブ
今回の特集「わたしと熊谷守一2026」は、2026年2月22日(日)午前9時分から9時45分までの45分間、NHK Eテレにて全国放送されます。この「45分」という枠組みこそが、日美(にちび)の伝統的なリズムです。
特筆すべきは、2026年という年が、1976年に産声を上げた番組にとってちょうど50周年のメモリアルイヤーであることです。今回の放送では、最新の4K・8K超高精細カメラで捉えた守一の肉筆画と、1970年代に16mmフィルムで撮影された貴重な取材映像が、時空を超えて交錯します。デジタルリマスターされた過去の映像には、晩年の守一が庭の土をいじる指の汚れや、愛用の眼鏡に反射する光までが鮮明に蘇っており、視聴者はあたかも50年前の守一の自宅にタイムスリップしたかのような錯覚を覚える構成となっています。
番組ロゴとテーマ曲の変遷:私たちの耳と目に焼き付いた「日曜の音」
『日曜美術館』を語る上で欠かせないのが、視聴者の脳裏に刻まれた五感の記憶です。歴代のテーマ曲は、番組の顔として時代を彩ってきました。 初代テーマ曲から、池辺晋一郎氏、そして近年の現代音楽家による繊細なアンサンブルまで、その音色は常に「日曜の朝の静謐」をデザインしてきました。2026年の特別企画では、これら歴代のテーマ曲がセクションごとに劇伴として使用されるという、ファン垂涎の演出が予定されています。
また、番組のタイトルロゴの変遷も、日本のグラフィックデザイン史そのものです。力強い筆文字の時代から、洗練されたモダンなフォントへと変化しながらも、常に画面中央に凛として佇むその姿は、番組が守り続けてきた「普遍的な美」の象徴です。今回の特集では、熊谷守一が好んで書いた独特の「守一文字」へのオマージュを込めた、特別仕様のアートワークが画面を彩ります。
Eテレが守り抜く「教養」の最後の砦:視聴率を超えた価値の創造
民放の美術番組が縮小・淘汰される中で、なぜ『日曜美術館』だけが、これほどまでの熱狂を維持し続けているのでしょうか。それは、NHK Eテレがこの番組を単なる「情報の伝達」ではなく「公共財としての芸術体験」と位置づけているからです。
1976年の開始当初から、番組は「わかりやすさ」よりも「作品との対話」を優先してきました。ナレーションで全てを説明せず、数秒間の「沈黙」を恐れない編集。作品の細部をじっくりと見せる長いフィックス(固定)ショット。これらの手法は、タイパ(タイムパフォーマンス)が重視される2026年のメディア環境において、極めて贅沢で挑戦的な「スローメディア」の姿勢を貫いています。名古屋放送局をはじめとする各地域の局が連携し、全国各地の美術館と視聴者を結ぶそのネットワークは、日本人の美意識を底上げしてきたといっても過言ではありません。今回の守一特集もまた、視聴率という物差しでは測れない、日本文化の豊かさを証明する放送となるでしょう。
4. 主要出演者・スタッフの徹底分析:言葉と感性の化学反応
『日曜美術館』が他の美術番組と一線を画す最大の要因は、出演者に「解説」ではなく「対話」を求めている点にあります。特に50周年特集「わたしと熊谷守一2026」では、専門家による美術史的な講義を排し、一人の表現者が守一の宇宙に飛び込むという、極めてパーソナルで濃密な構成が取られています。
案内人・皆川明の眼差し:デザイナーが読み解く守一の「形態」と「色面」
今回の案内人を務めるのは、ファッションブランド「minä perhonen(ミナ ペルホネン)」のデザイナー、皆川明さんです。皆川さんの起用は、2026年の視聴者にとって最も幸福なマッチングと言えるでしょう。皆川さんが描くテキスタイルの図案には、自然界の動植物への深い敬意と、繰り返されるパターンの心地よさがあります。これは、晩年の守一が庭という小宇宙で発見した「命の反復」と見事に共鳴します。
皆川さんは、守一の絵の前で多くを語りません。しかし、その沈黙の後に発せられる「この赤い線は、血の巡りそのものですね」といった、デザイナーならではの身体感覚に基づいた言葉は、既存の美術評論を鮮やかに超えていきます。皆川さんの視線は、キャンバスの端にまで及び、守一が何を切り捨て、何を残したのかという「デザイン的決断」を読み解いていきます。この「創り手同士の魂の交信」こそが、今回の放送の核となっています。
歴代キャスターが繋いだバトン:専門家ではない「表現者」を起用し続ける演出意図
番組開始から50年、歴代のキャスターには俳優、詩人、作家、ミュージシャンなど、多彩な顔ぶれが並んできました。あえて美術の専門家ではない「言葉のプロ」を据えるのは、視聴者の隣に立つ「等身大の感動」を大切にしているからです。
かつての檀ふみさんや、近年の小野正嗣さんのように、作品を前にして驚き、迷い、時には言葉を失う姿。そのプロセスそのものを放映することで、視聴者は「正解を探す鑑賞」から解放されます。2026年の特集でも、これら歴代キャスターたちが守一の作品と向き合った際の「言葉の断片」が随所に挿入されます。時代によって、同じ守一の絵から受け取るメッセージがどう変化してきたのか。それは、日本人の感性の変遷を辿るドキュメンタリーでもあるのです。
演出家とナレーターの職人芸:静寂をデザインする「間」の美学
『日曜美術館』のクオリティを最終的に担保しているのは、ナレーションの「温度」と「間」をコントロールするスタッフの職人芸です。今回の特集では、抑制の効いた語り口で定評のあるナレーターが起用され、情報の詰め込みすぎを徹底的に排除しています。
特筆すべきは、守一の作品が画面に映し出される際、数秒間、完全に音を消す「完全な静寂」の演出です。テレビにおいて無音は放送事故に近いリスクを伴いますが、日美のスタッフは「静寂もまた守一の作品の一部である」と考え、勇気を持って音を削ぎ落とします。視聴者は、スピーカーから流れるホワイトノイズの中に、守一の庭に吹く風や、虫の羽音を想像する。この「視聴者の想像力を信じる」演出こそが、50年間変わらぬ日美のプライドであり、2026年の放送でも遺憾なく発揮されているのです。
5. 伝説の「神回」アーカイブ:日美が捉えた熊谷守一の記憶
番組が50年間で積み上げた守一特集は、単なる画業の紹介に留まりません。時代ごとに異なる「守一像」を提示し、視聴者の価値観を揺さぶってきました。2026年の放送では、これらの過去映像が最新のデジタル技術で修復され、多層的な物語として編み直されています。
1977年、没直後の衝撃:実娘・熊谷榧が語った「父の真実と仙人像の乖離」
守一が97歳でこの世を去った直後、1977年に放送された追悼特集は、今なお語り継がれる「伝説の回」です。世間では「超然とした仙人」として神格化され始めていた守一に対し、実娘であり画家でもあった熊谷榧(かや)さんが語った言葉は、視聴者に衝撃を与えました。
「父は仙人などではなく、ただただ、見ることに執着した一人の人間でした」。 榧さんがカメラの前で、父が庭の石を拾い上げ、その重さや質感を確かめる様子を再現したシーンは、守一の芸術が「観念」ではなく「壮絶な観察」から生まれていたことを証明しました。16mmフィルム特有の粒子の粗い映像の中で、守一の遺品である使い古された絵筆や、絵具の跡がこびりついたパレットが映し出された瞬間、スタジオには言いようのない沈黙が流れました。2026年の特集では、この榧さんの証言映像が、守一の絶筆とされる作品と共に再構成され、彼の「人間としての体温」を現代に蘇らせます。
1985年、百一歳を越えて:再評価の嵐の中で番組が提示した「モダニズムとしての守一」
1980年代、バブル経済へと向かう狂騒の中で放送された特集は、守一を「隠遁者」としてではなく、徹底した「モダンな造形家」として切り取りました。当時の番組スタッフは、守一の代名詞である「赤い輪郭線」に注目し、それをマティスやルオーといった西洋近代絵画の文脈と対比させる大胆な試みを行いました。
この回で視聴者を釘付けにしたのは、守一が描く「猫」や「鳥」のフォルムが、実は極めて数学的なバランスで構成されていることを指摘したシーンです。カメラは作品に極限まで寄り、単色で塗りつぶされた背景の「色面の強さ」を強調しました。経済が膨張し、過剰な装飾に溢れていた80年代の日本において、守一の「引き算の美学」は、逆説的に最もアヴァンギャルド(前衛的)なものとして映りました。2026年の視点から見ても、この時の分析の鋭さは全く色褪せていません。
2000年代、4Kで蘇る色彩:科学の眼が捉えた「守一の赤」の正体
デジタル放送への移行期に制作された2000年代の特集では、最新の光学解析技術が導入されました。守一の絵画の特徴である、あの独特な「赤」をどう再現するか。番組は、守一が愛用していた絵具の成分分析まで踏み込み、彼がなぜあの色を選んだのかを視覚的に解明しようと試みました。
高精細カメラが捉えたのは、一見平坦に見える色面の中に隠された、驚くべき「筆の運び」の複雑さです。番組は、守一が一度塗った色を、乾かないうちに別の色で削り取るような技法を使っていたことを映像で証明しました。それは、ただ「シンプルに描く」ことの裏側に、どれほど残酷なまでの「選択と集中」があったかを物語っていました。2026年の放送では、この科学的な視点がさらに進化し、ホログラム技術のような立体的な映像解析を用いて、守一の絵画の中に流れる「時間の層」を解き明かしていきます。
6. 視聴者の熱狂とコミュニティ分析:#日美 が生む知的サロン
かつてテレビは「一方通行のメディア」でした。しかし、『日曜美術館』に関してはその常識は当てはまりません。特にこの10年、SNSの普及とともに、この番組は「視聴後に誰かと語り合いたくなる」知的な交流のハブとなりました。2026年2月22日の「わたしと熊谷守一」放送時、ネット上ではどのような現象が起きるのか。その熱狂の構造を分析します。
日曜朝のSNS現象:リアルタイムで交わされる「#日曜美術館」の深い考察
日曜午前9時。X(旧Twitter)などのSNSでは、ハッシュタグ「#日曜美術館」や、ファンによる略称「#日美」が瞬く間にトレンド入りします。驚くべきは、その投稿内容の「解像度の高さ」です。
「今の守一の『蟻』のカット、光の入り方が計算され尽くしている」「皆川明さんの言葉が、自分の仕事の悩みとリンクして涙が出た」といった、単なる感想を超えた批評的なコメントがリアルタイムで流れていきます。視聴者はテレビ画面とスマホのタイムラインを往復しながら、全国に散らばる見知らぬ「美の求道者」たちと感動を共有します。2026年の現在、このハッシュタグはもはや単なる感想ログではなく、放送と同時に編み上げられる「もう一つの副読本」としての機能を果たしているのです。
ファンが愛する「日美構図」:視聴者が真似したくなる美術館の歩き方
長年のファンの間では、番組のカメラワークをリスペクトした「日美構図」という概念が定着しています。それは、作品の全体像を見る前に、あえて「額縁の隅」や「キャンバスの裏側」「画家の手元」といった細部に注目し、そこから全体を想像する鑑賞スタイルです。
今回の守一特集においても、放送翌日には全国の「熊谷守一美術館」やゆかりの地に、多くの視聴者が訪れることが予想されます。彼らは番組で紹介された「守一が見つめた角度」を再現しようと、庭の地面を這う蟻にレンズを向けたり、木漏れ日の揺らぎをじっと見つめたりします。番組が提供するのは知識ではなく、「世界の見方」そのものなのです。この「番組を観て、実際に動く」という高い行動力こそが、日美ファンの最大の特徴です。
「守一ファン」という静かな連帯:シンプルさを追求する現代のライフスタイルへの影響
熊谷守一という画家の人気は、現代のライフスタイルとも深く結びついています。モノを減らし、本質だけを愛でる「ミニマリズム」を志向する層にとって、守一はまさに精神的支柱です。
番組のコミュニティでは、守一の絵画だけでなく、彼の「一切の虚飾を排した生き方」についての議論がしばしば熱を帯びます。「私たちは、守一のように45分間も一つの花を見つめられるだろうか?」という自省的な問いかけ。それは、効率化を極めた2020年代の社会に対する、静かな抵抗のようにも思えます。2026年の特集は、こうした「心の豊かさ」を求める視聴者たちの連帯をさらに強固なものにし、「日美」という番組を、単なるテレビ番組から「より良く生きるための指針」へと昇華させているのです。
7. マニアが唸る「重箱の隅」ポイント:細部に宿る制作の魂
『日曜美術館』を数十年見続けているマニアは、単に作品を見るだけでなく、番組そのものを「一つの工芸品」として鑑賞します。特に今回の50周年特集「わたしと熊谷守一2026」では、スタッフの並々ならぬ気合いが、音、編集、さらにはテロップのミリ単位の配置にまで及んでいます。
BGM選曲の妙:今回の特集で流れる音楽と守一の「リズム」の共鳴
日美の選曲センスは、放送業界でも随一と言われています。クラシックの定番から、現代音楽、時にはアンビエントな電子音まで、その引き出しの多さは驚異的です。 今回の守一特集でマニアが注目すべきは、守一が描く「命のリズム」に合わせた選曲です。例えば、蟻が歩くシーンに流れるのは、装飾を削ぎ落としたミニマム・ミュージック。守一がキャンバスに引く一本の線に合わせて、チェロの単音がスッと重なる瞬間。音楽が作品を説明するのではなく、作品が持つ「固有の波長」を増幅させるような音作りがなされています。放送後には「あの曲は何?」という問い合わせが殺到するのが日美の常ですが、2026年の本作でも、音楽家・皆川明の感性と響き合うような、静謐でいて力強いプレイリストが画面の奥行きを広げています。
編集の「癖」を読む:カット割りで見せる「画家の視線の動き」の再現
日美の編集には、伝統的な「癖」があります。それは、作品を映す際に「まず視点を一箇所に固定し、そこからゆっくりと、あたかも肉眼が動くようにパン(移動)させる」という手法です。 特に守一の作品は、極限まで単純化されているため、どこに視点を置くかが重要です。マニアは、編集マンがどの「輪郭線」を起点にカメラを動かしたかを見ています。今回の2026年版では、守一が実際に対象を観察していた時間軸を編集テンポに反映させており、あえて「じれったいほど長い」カットが挿入されています。この「待たせる編集」こそが、視聴者の脳を「守一モード」へと強制的に切り替えるスイッチとなっているのです。
テロップのフォントまでこだわる:画面全体を一枚の「作品」にするアートディレクション
美術番組において、文字情報は時に作品の邪魔になります。日美が50年かけて磨き上げたのが、この「テロップの消し方」の美学です。 2026年の特集では、テロップのフォントに、守一の素朴な書体にインスパイアされたオリジナルのウェイトが使用されているという噂があります。文字が画面に現れる際も、パッと出るのではなく、和紙に墨がじわっと染み込むようなフェードインを採用。背景となる絵画の色彩を邪魔しないよう、輝度や透明度が1%単位で調整されています。マニアは、左下に小さく表示される「作品名・年次」の文字が、作品の構図を壊さない「空きスペース」に完璧に配置されていることに、スタッフの芸術的良心を感じ取るのです。
8. 総評と未来予測:テレビ界における『日曜美術館』の意義
「わたしと熊谷守一2026」という45分間の旅を終えたとき、私たちの手元に残るのは、単なる美術の知識ではありません。それは、50年という歳月をかけて番組が耕してきた「視ること」への誠実な態度です。テレビというメディアが、情報の速報性や消費の快楽に傾倒していく中で、『日曜美術館』が守り抜いた静寂は、2026年の今、どのような意味を持つのでしょうか。
失われない価値:オンデマンド時代における「放送」というライブ体験の強み
2020年代後半、動画配信サービスが完全に主流となった今でも、『日曜美術館』を日曜午前9時に「リアルタイムで視聴する」という行為には、特別な高揚感が伴います。それは、日本中の数万人が、同じ瞬間に同じ一枚の絵を見つめ、同じ沈黙を共有するという「公衆の体験」だからです。
オンデマンドでいつでも見られる利便性は素晴らしいものですが、日美が提供するのは、日曜の朝という清浄な時間帯に、自らの感性を「調律」する儀式に近い体験です。2026年の特集は、画一的なアルゴリズムが提示する「おすすめ」ではなく、編集者の確固たる意志によって編まれた「一期一会の45分間」の価値を再定義しました。この「予約された静寂」こそが、テレビ放送が未来へ生き残るための数少ない、しかし強力な武器となるはずです。
AI時代のアート鑑賞:人間が「美しい」と感じる瞬間の言語化に挑み続ける
AIが瞬時に絵画を生成し、完璧な美術評論を書き上げる時代において、私たちは何をもって「美」を判断すべきなのでしょうか。その答えの一端が、案内人・皆川明さんの言葉にありました。 皆川さんが守一の作品から感じ取った「生命の脈動」や「制作の苦しみ」は、データに基づいた分析ではなく、人間が生身の身体を持って世界と対峙したときにしか生まれない「震え」です。番組が50年間続けてきたのは、この言語化不能な「震え」を、なんとか言葉と映像で繋ぎ止めようとする試行錯誤でした。AIに答えを求めるのではなく、自分自身の眼で見て、戸惑い、発見する。その人間らしい泥臭いプロセスを肯定し続ける限り、この番組の使命が終わることはありません。
100年目の日美へ:次世代に語り継ぐべき「命の本質をみつめる」という姿勢
熊谷守一は、庭というわずか数坪の空間に宇宙を見出しました。『日曜美術館』もまた、45分という限られた枠の中に、人類が数千年にわたって積み上げてきた美の遺産を凝縮してきました。 2026年の50周年特集は、通過点に過ぎません。これから50年後の「100周年」を迎えるとき、世界がどれほどデジタル化されていたとしても、私たちが「命の本質」を希求する心は変わらないでしょう。
「わたしと熊谷守一2026」が私たちに教えてくれたのは、世界はいつだって見られるのを待っている、ということです。一匹の蟻、一輪の花、そして一枚の絵。それらを深く見つめることは、自分自身の生を慈しむことと同義です。日曜午前9時、あのお馴染みのテーマ曲が流れる限り、私たちの美への旅は終わることはありません。50年の歴史に敬意を表しつつ、私たちはさらなる深淵へと歩みを進めるのです。