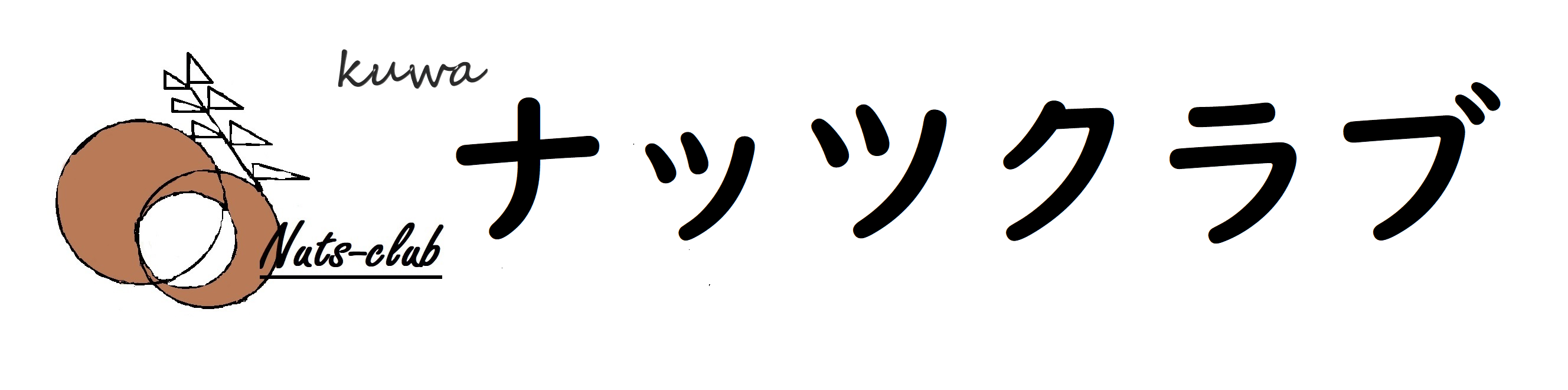1. 導入:10分間に凝縮された「地球の鼓動」と究極の没入感
なぜ今、私たちは「最果て」の車窓を求めているのか
情報が溢れ、あらゆる場所がスマートフォン一つで検索できてしまう現代において、私たちは逆説的に「本当の未知」に飢えています。2月21日、土曜日の夜20時45分。週末の喧騒が少しずつ落ち着きを見せ始めるこの時間帯に、NHK Eテレが差し出すのは、美食でもスキャンダルでもない、ただひたすらに続く「線路」と「雪原」の風景です。
『行くぞ!最果て!秘境×鉄道ミニ』。このタイトルが示す通り、私たちが目にするのは、観光ガイドブックの数ページを飾るような華やかな北欧ではありません。そこにあるのは、人間が容易に立ち入ることを拒む、剥き出しの自然です。ノルウェー・オスロから北極圏の町ボードーまで1,280キロ。この果てしない距離を、鉄の塊が雪を蹴立てて進む姿に、私たちはなぜこれほどまでに惹きつけられるのでしょうか。それは、効率やスピードを重視する日常から切り離された「異界」へのパスポートを、この番組が提示してくれるからに他なりません。画面越しに伝わる極寒の空気、静寂を切り裂く列車の走行音。それらは、私たちが忘れかけていた「移動」という行為の根源的な冒険心を、静かに、しかし強烈に呼び覚ますのです。
ミニ番組という枠を超えた、NHKクオリティの「映像美」という暴力
「たった10分の番組でしょ?」と侮るなかれ。この番組における10分間は、最高級のステーキから余分な脂を削ぎ落とし、旨味だけを凝縮したエッセンスのようなものです。特に今回の「ノルウェー・NSB鉄道(2)」において、NHKの撮影クルーが提示した映像クオリティは、もはや「暴力」的なまでの美しさを誇っています。
特筆すべきは、その圧倒的な色彩設計です。北極圏に近い冬のノルウェーは、太陽が低く、独特の「青」が世界を支配します。雪原に落ちる影の深い紺色、朝焼けに染まる薄氷のピンク、そしてNSB鉄道の車両が放つ力強い赤。これらのコントラストが、最新の撮影機材によって極限まで鮮明に捉えられています。視聴者は、4K/8K時代を象徴するような高精細な映像によって、あたかも自分が列車の先頭車両に張り付いているかのような錯覚に陥ります。過剰なナレーションやテロップで情報を詰め込むのではなく、映像そのものに語らせる。この「引き算の美学」こそが、数ある紀行番組の中でも本作を際立たせている最大の要因と言えるでしょう。
ノルウェー編第2回が提示する、北極圏という「非日常」への招待状
今回のエピソードがフォーカスするのは、旅のハイライトとも言える「北極圏突入」のプロセスです。オスロを出発した列車が北上を続け、ついに北緯66度33分のラインを越える瞬間。そこから先は、私たちが知る「冬」とは次元の異なる世界が広がっています。
番組が描くのは、単なる移動の記録ではありません。そこには、大雪原をただ独り疾走する列車の「孤独な勇姿」があります。ドローンカメラが上空数百メートルから捉えた映像では、巨大な山脈の足元を、まるでおもちゃのような細い一本の線が這うように進んでいきます。この「巨大な自然 vs 矮小な人間(鉄道)」という構図の対比が、見る者に畏怖の念を抱かせます。さらに、番組は絶景だけに終始しません。極寒の地で脈々と受け継がれる先住民サーミの暮らしや、フィヨルドの小さな村で育まれるハンドメイドのぬくもりなど、冷たい氷の世界の中に灯る「人の営みの温かさ」を絶妙なバランスで差し挟んできます。この温度差こそが、10分間という短い旅路を、一生忘れられない体験へと昇華させているのです。
2. 基本データ:鉄路1280キロを繋ぐ「NSB鉄道」の全貌
オスロからボードーへ、北欧を縦断する大動脈のスペック
今回、番組が追いかける「NSB(ノルウェー国鉄)」の路線は、首都オスロを起点に北上を続け、北極圏の入り口であるボードー(Bodø)までを結ぶ、総延長約1,280キロに及ぶ鉄路の旅です。この距離は、日本で言えば東京から鹿児島までを優に超える長大なもの。しかし、その中身は日本の新幹線のような効率化された移動とは一線を画します。
特筆すべきは、ノルウェー最長の鉄道路線である「ヌールラン鉄道(Nordland Line)」を含むルート設定です。この路線は、電化されていない区間も多く、力強いディーゼル機関車が雪煙を上げて進む姿が鉄道ファンの心を掴んで離しません。最高時速を競うのではなく、フィヨルドの断崖を縫い、凍てつく湖畔をかすめ、標高の高い峠を越えていく。その過酷な環境に耐えうる北欧設計の車両は、車内こそモダンで快適な北欧デザインが施されていますが、外見は厳しい自然と戦う「鉄の野獣」そのもの。このメカニカルな力強さと、窓の外に広がる静謐な雪景色のコントラストこそ、NSB鉄道が「世界で最も美しい車窓の一つ」と称される所以なのです。
Eテレ20時45分、週末の夜に訪れる「10分間の静寂と興奮」
本作が放送される「土曜 20:45〜20:55」という時間枠は、NHKの編成戦略における「至高のエアポケット」と言えます。大河ドラマの余韻が残り、夜のニュースや大型バラエティが始まる直前のこの10分間。視聴者の脳が適度に疲れ、何かに癒やされたいと願う絶妙なタイミングで、この番組は流れます。
Eテレというチャンネル特性上、教育的な側面を持ちつつも、本作は極めて「感覚的」なアプローチを取っています。民放の紀行番組にありがちな、大げさなBGMやタレントの騒がしいリアクション、画面を埋め尽くす派手なテロップは一切排除されています。代わりに用意されているのは、氷を割る音、風の唸り、そして規則正しいレールの継ぎ目音。この「情報の余白」が、視聴者の想像力を刺激します。10分間という短尺だからこそ、視聴者は集中力を切らすことなく、画面の中の北極圏へとダイブすることができるのです。それはテレビ視聴というよりは、むしろ「動く写真集」をめくるような、極めて贅沢な読書体験に近い感覚を視聴者に提供しています。
ミニ版ならではの構成美:情報を削ぎ落とし、感覚を研ぎ澄ます演出
『行くぞ!最果て!秘境×鉄道』には、長尺の本編(BS等での放送)が存在しますが、この「ミニ」版には、長尺版にはない独特の鋭さがあります。制作陣は、数時間にも及ぶ膨大な素材の中から、ダイヤモンドの原石を磨き出すようにカットを厳選しています。
その編集ルールは徹底されています。例えば、一つの景観カットをあえて長く保つことで、光の移ろいや雪の結晶の煌めきをじっくりと見せる手法。あるいは、あえて列車の全景を映さず、車輪が雪を弾き飛ばすクローズアップから入ることで、極寒の地の「質感」を伝える演出。これらは、10分間という制約を「制限」ではなく「武器」として捉えた、プロの職人技の結晶です。視聴者は、断片的な映像の連なりから、1,280キロという旅の広がりを脳内で補完し、自分だけの旅路を完成させていく。この「不親切なほどのシンプルさ」が、結果として最高の没入感を生んでいるのです。
3. 番組の歴史・制作背景:秘境を「切り取る」撮影隊の執念
「秘境×鉄道」シリーズが守り続ける、定点観測と移動の美学
NHKが長年培ってきた紀行番組のノウハウを、極限まで「純化」させたのがこのシリーズです。かつての紀行番組が「タレントが現地の人と触れ合う」という人間ドラマに重きを置いていたのに対し、本シリーズが徹底しているのは、鉄道という「移動する視点」そのものを主役に据えることです。
番組の歴史を遡れば、それは単なる風景紹介ではなく、刻一刻と変化する「地球の表情」を記録するアーカイブとしての側面が見えてきます。特にノルウェー編のような極北の地では、撮影のチャンスは一瞬。太陽が地平線スレスレを移動する「ブルーアワー」や、吹雪が止んだ直後の無垢な雪原など、計算し尽くされたスケジュールと、それ以上に過酷な「待ち」の時間によって、10分間の奇跡は作られています。制作陣が守り続けるのは、安易なズームやパンを多用せず、風景が持つ力強さをそのまま受容する「定点観測」の精神。その揺るぎない視点が、視聴者に「今、自分もこの列車に乗っている」という、揺るぎない実感を抱かせるのです。
極寒のノルウェーロケ:マイナス数十度の世界で回るカメラの裏側
「ノルウェー・NSB鉄道(2)」の舞台となる北極圏は、カメラ機材にとっても、撮影スタッフにとっても地獄のような環境です。外気温はマイナス20度、30度は当たり前。金属製の三脚は素手で触れれば皮膚が張り付き、バッテリーは通常の数分の一の時間で空になります。
このセクションで特筆すべきは、番組が捉える「音」と「光」のリアリティです。撮影クルーは、車内の暖かなラウンジで優雅にレンズを向けているわけではありません。極寒の駅のホームや、人里離れた雪原のど真ん中に三脚を立て、列車が通過するわずか数秒のために何時間も耐え忍びます。画面に映る、列車のフロントガラスを叩く細かな雪の結晶や、排気筒から上がる真っ白な蒸気。これらは、防寒装備を完璧に整えたスタッフが、凍てつく指先でフォーカスを合わせ続けた証です。この「現場の体温」が、冷たい映像の奥底から視聴者の心に熱く伝わってくる。それこそが、単なるドキュメンタリーを超えた、プロフェッショナルの仕事なのです。
最新鋭ドローンが捉えた「誰も見たことのない」鉄路の曲線美
今回の放送で、視聴者の度肝を抜くのが「見たことないすごいドローン映像」です。かつての鉄道番組における空撮といえば、ヘリコプターからの引きの映像が主流でしたが、本作ではドローンを駆使し、列車の屋根スレスレから、フィヨルドの断崖絶壁へと一気に視界が開けるような、ダイナミックなカメラワークを披露しています。
特に、フィヨルドの複雑な地形を縫うように走るNSB鉄道の姿を、真上から、あるいは並走しながら捉えたカットは圧巻です。雪に閉ざされた無人の大地に、一本の黒い線(レール)が描かれ、そこを赤い列車が力強く突き進んでいく。この俯瞰の視点は、地上からは決して味わえない「自然のスケール感」と「鉄道の孤独なプライド」を同時に描き出します。ドローンパイロットの神業とも言える操作によって、冷徹なまでに美しいノルウェーの大地が、まるで生き物のように躍動して見える。この映像体験こそが、現代のテレビが到達した一つの「極北」と言えるでしょう。
4. 主要出演者・スタッフの徹底分析:声と視線が作る「旅情」
ナビゲーター(語り)が果たす、視聴者の「耳」としての役割
『行くぞ!最果て!秘境×鉄道ミニ』において、ナレーションは単なる状況説明の手段ではありません。それは、視聴者を現実世界から北緯66度の極寒の地へと誘う「ガイド」であり、共犯者でもあります。この番組の語り口に共通しているのは、抑制の効いた、それでいて知的好奇心に満ちたトーンです。
例えば、吹雪の中を突き進むNSB鉄道の勇姿が映し出される際、ナレーターは過度に叫んだり感動を押し付けたりしません。「雪を切り裂き、列車はさらに北へ……」といった、短く、詩的なフレーズを置く。その「間の取り方」が絶妙なのです。視聴者はその静かな声に導かれ、自分自身の思考を映像に投影する余白を与えられます。饒舌すぎないナレーションこそが、10分間という限られた時間の中で、視聴者を深い没入状態(ゾーン)へと引き込む重要なスイッチとなっているのです。
現地の人々の表情を引き出す、ディレクターの卓越した距離感
この番組の隠れた主役は、列車の乗客や沿線で暮らす人々です。ノルウェー編第2回では、先住民サーミの人々やフィヨルドの小さな村の住人が登場しますが、彼らの捉え方が極めて秀逸です。カメラは決して彼らを「珍しい存在」として消費しません。
ディレクターは、彼らが代々受け継いできたトナカイとの関わりや、冬の長い夜を彩るハンドメイドの小物作りなど、その「手元」や「眼差し」を丁寧に拾い上げます。インタビューで多くを語らせるのではなく、作業に没頭する横顔や、ふとした瞬間にカメラに向ける穏やかな微笑みを捉える。そこには、言葉の壁を越えた、撮影スタッフと現地の人々との間に築かれた「信頼の温度」が確かに存在します。この温かな視点があるからこそ、冷徹なまでの大自然の映像が、血の通った「人間の物語」として私たちの胸に響くのです。
音楽と環境音のシンフォニー:モーター音と雪を踏む音の重要性
本作を語る上で絶対に欠かせないのが、音響デザイン(MA)のクオリティです。この番組は、音楽で感情をコントロールするのではなく、徹底的に「環境音」を主役に据えています。
列車の重厚なモーター音、レールが軋む高い金属音、そして停車した駅で聞こえる、キュッキュッと雪を踏みしめる乾いた音。これらの音が、驚くほど鮮明に、立体的にミックスされています。最新の録音技術を駆使して集音されたこれらの「現場の音」は、視覚情報を補完し、視聴者の肌に冷気を伝える役割を果たしています。そこへ、北欧の静寂を象徴するような透明感のある劇伴が、薄氷のように重なる。この緻密な音の設計こそが、10分間の放送を、まるで高品質なオーディオドラマを聴いているかのような、五感を刺激する体験へと変貌させているのです。
承知いたしました。いよいよ今回の放送のハイライト、10分間の映像の中に刻まれた「奇跡の瞬間」を、テレビコラムニストの視点で克明に描写していきます。
5. 伝説の「神回」アーカイブ:ノルウェー編第2回・3つの決定的一瞬
北極線(アークティック・ライン)通過:無人銀世界を切り裂く列車の咆哮
今回のエピソードにおいて、最も視聴者の心拍数を跳ね上げる瞬間は、列車が「北緯66度33分」の境界線、すなわち北極線を越えるシーンです。画面に映し出されるのは、人工物が一切排除された、見渡す限りの純白の雪原。そこを、NSB鉄道の赤い車体が、まるでもののけ姫に登場する乙事主(おっことぬし)のような力強さで、雪煙を高く巻き上げながら疾走します。
特筆すべきは、その「音」と「光」の演出です。北極圏に突入した瞬間、太陽の光はさらに斜光となり、雪面は微細なダイヤモンドダストを含んだような、刺すような輝きを放ちます。ドローンが列車の真横を並走し、車輪が線路上の氷を粉砕する「ガガガッ」という重低音を拾い上げたとき、視聴者はテレビの前にいながらにして、極限の地の冷気と振動を肌で感じることになります。この「北極線通過」という概念的な境界を、映像の圧倒的な質感で「物理的な突破」として描き出した演出は、まさに神業と言えるでしょう。
先住民サーミの知恵:トナカイを見分ける「瞳」と「伝統」の深淵
絶景の興奮が冷めやらぬ中、番組は静かに「人の営み」へとカメラを向けます。北欧の先住民、サーミの人々。彼らが吹雪の中でトナカイの群れと対峙するシーンは、この番組が単なる鉄道趣味番組ではないことを証明しています。
マニアが唸るのは、彼らの「トナカイの見分け方」に迫るカットです。数百頭、数千頭とひしめき合うトナカイの群れの中から、彼らは耳の切り欠きや角の形、わずかな毛色の違いを一瞬で見抜きます。カメラは、サーミの長老の深く刻まれたシワと、その奥にある鋭くも優しい瞳をクローズアップで捉えます。過酷な自然を「敵」とするのではなく、その一部として共生してきた彼らの哲学が、一言のナレーションよりも雄弁に語りかけてくるのです。雪原に散らばるトナカイの足跡と、それを追うサーミのソリ。鉄道という近代の産物と、数千年来変わらない伝統が交差するこの瞬間こそ、本エピソードの精神的な白眉(はくび)です。
フィヨルドの小さな村:ハンドメイド小物が語る、過酷な自然との共生
旅の終盤、列車はフィヨルドの深い入り江にひっそりと佇む小さな村に停車します。ここで紹介される、色鮮やかな毛糸で編まれたハンドメイドの小物は、モノトーンの雪の世界に差し込まれた「生命の灯火」のように見えます。
カメラワークの妙が光るのは、村の女性が編み物をする手元のアップから、窓の外に広がる巨大なフィヨルドの絶壁へとフォーカスを移す一連の流れです。家の中の「静」と、外の世界の「動」。この対比によって、厳しい冬を乗り越えるための知恵としての「手仕事」の尊さが浮き彫りになります。手袋や帽子に施された独特の幾何学模様は、北欧の厳しい自然への敬意と、家族を想う温かさの象徴。10分という短い時間の中で、広大な大地のスケール感から、人の指先が紡ぎ出すミクロな美しさまでを網羅する構成力には、脱帽するほかありません。
6. 視聴者の熱狂とコミュニティ分析:ハッシュタグに集うマニアたち
SNSを席巻する「#秘境鉄道」:静止画のようなキャプチャが溢れる理由
放送時間の20時45分。X(旧Twitter)を中心としたSNSでは、「#秘境鉄道」「#行くぞ最果て」といったハッシュタグが、まるで見えない合図があったかのように一斉に動き出します。この番組のSNS上の特徴は、驚くほど「キャプチャ画像」の投稿が多いことです。しかも、それらは単なる記録ではなく、一枚の風景写真として完成された、極めて審美眼の高いものばかりです。
視聴者たちは、ドローンが捉えたノルウェーの青い雪原や、フィヨルドの鏡のような水面を、まるで宝探しをするようにスマートフォンの画面に収めます。そこには、バラエティ番組で見られるような爆笑のコメントはほとんどありません。代わりに並ぶのは、「美しすぎて言葉が出ない」「10分間で心拍数が落ち着いた」「この青色(ノルウェー・ブルー)をずっと見ていたい」といった、静かな感動の吐露です。情報の洪水に疲れた現代人にとって、この10分間は「SNS映え」を超えた「魂の洗濯」の場となっているのです。
鉄道ファン・旅好き・写真愛好家、三位一体の熱い支持層
この番組のファン層は、驚くほど多層的です。まず中心にいるのは、NSB鉄道の車両型式やレールの軌間までをチェックする**「鉄道マニア」**たち。彼らにとって、ディーゼル機関車が吐き出す煙の量や、雪を跳ね飛ばすスノープラウの角度は、何杯でも酒が飲める「肴」となります。
しかし、その隣には「いつかここへ行きたい」と願う**「旅好き」、そして映像の構図やカラーグレーディング(色彩補正)の妙を分析する「映像・写真愛好家」**が肩を並べています。この異なる属性のファンたちが、一つの番組を通じて「北極圏の美」という一点で共鳴し合っているのが本シリーズの特異点です。鉄道ファンが車両の解説をし、旅好きがフィヨルドの歴史を語り、写真好きが光の当たり方を称賛する。この健全かつ知的な情報交換が、番組の放送をきっかけに毎週繰り広げられているのです。
ファンが考察する「BGMの選曲センス」と「編集の間」
さらにコアなファンの間では、番組の「編集」そのものが考察の対象となっています。特に今回のノルウェー編では、あえて「無音」に近い瞬間を数秒間作る、NHKの編集マンの胆力が話題となります。
「今の3秒間の沈黙が、北極圏の孤独を完璧に表現していた」「このタイミングで入る北欧ジャズ風のBGM、選曲センスが神がかっている」。そんな玄人好みの感想が飛び交います。視聴者はただ受動的に見ているのではなく、制作陣が映像の裏側に仕込んだ「意図」を読み解こうとするのです。あるファンは、列車の走行音とBGMの音量バランス(フェーダーさばき)を分析し、別のファンは10分間という尺の中で「絶景」と「生活」が交互に現れる黄金比について熱弁を振るいます。このように、視聴者が作り手と同じ目線で作品を愛でる文化が、強固なコミュニティを形成しているのです。
7. マニアが唸る「重箱の隅」ポイント:細部に宿る北欧の魂
列車の「着雪」具合で推察する、現地の極限状態
マニアが画面を食い入るように見つめるのは、走行するNSB鉄道の「連結部」や「台車(車輪周り)」です。今回のノルウェー編第2回、特に北極圏突入後のシーンでは、車両の隙間にガチガチに固まった氷の塊、いわゆる「着雪」の質感が驚くほど鮮明に映し出されています。
この氷の付き方一つで、現地の湿度が低く、いかにサラサラとした極寒の雪であるかが分かります。制作陣は、あえてこの「美しくないはずの氷の塊」をクローズアップで挿入します。それは、この鉄道が単なる観光列車ではなく、氷点下30度の世界で人々の生活を支える「ライフライン」であることを象徴しているからです。雪を噛み、氷を纏いながらも定刻通りに北極圏を突き進む――。鉄の表面に張り付いた結晶の煌めきに、マニアは北欧鉄道の「強靭な魂」を感じ取り、ひとり静かに快哉を叫ぶのです。
車窓に映り込む「光の屈折」:北極圏特有の淡いブルーの正体
映像美を語る際、多くの人は広大な風景に目を奪われますが、真の愛好家は「列車の窓ガラス」に注目します。北極圏の冬、太陽は地平線スレスレの角度から光を投げかけます。この低い太陽光が車窓の二重ガラスを通り抜け、車内に複雑な虹色のプリズムや、北欧特有の「ブルーモーメント(薄明)」の階調を作り出す瞬間を、カメラは見事に射抜いています。
特筆すべきは、その光の「柔らかさ」の表現です。空気が極限まで乾燥し、塵一つない北極圏の光は、私たちが日本で見る光とは波長が異なるかのように見えます。番組のカラーグレーディング(色彩調整)担当者は、この絶妙な「ノルウェー・ブルー」を再現するために、シャドウ部分の青を極限まで深く、しかし透明感を失わないよう調整しているはずです。窓に反射する雪原の白と、車内の暖かな照明が混ざり合う数秒のカット。そこに、テレビ放送の限界に挑む映像屋のプライドが隠されています。
数秒のカットに込められた、フィヨルドの村の「生活の残り香」
10分間の放送の中で、フィヨルドの村のカットは時間にしてわずか数十秒です。しかし、その短い映像の中に、マニアは「人々の暮らしの厚み」を読み取ります。例えば、家の軒先に吊るされた防寒着の揺れ方、あるいは窓辺に飾られた小さなキャンドルの火。
これらは一見、風景の一部に過ぎませんが、ディレクターは「そこにある生活」を記号化して配置しています。ノルウェーには「心地よい時間と空間」を意味する「ヒュッゲ(Hygge)」に近い文化がありますが、厳しい自然環境があるからこそ、家の中のわずかな温もりが尊い。番組は、カメラを大きく動かすことなく、ただ静かにそれらをフレームに収めます。村人が歩いた後に残る深い足跡、そこから立ち昇るかすかな湯気。こうした「音のない情報」を読み解くことこそ、この番組を100回楽しむための重箱の隅的な悦びなのです。
8. 総評と未来予測:テレビ界における「ミニ紀行番組」の意義
タイパ時代に逆行する「贅沢すぎる10分間」という価値
現代のコンテンツ消費は、倍速視聴やショート動画といった「タイムパフォーマンス(タイパ)」が支配しています。しかし、『行くぞ!最果て!秘境×鉄道ミニ』が提供しているのは、その真逆にある価値観です。10分という短い尺でありながら、そこには倍速では決して味わえない「時間の重み」が流れています。
ノルウェーの静寂を、1秒も飛ばさずに見つめる。雪原を横切る列車の音を、一切の雑音を排して聴く。この体験は、効率を求める日常への強力なアンチテーゼです。視聴者はこの番組を「情報を得るため」に見ているのではありません。「自分を取り戻すため」に見ているのです。情報を削ぎ落とし、ただ風景と同化する。この「贅沢な空白」を提供できるミニ番組という形式は、過剰な刺激に疲弊した現代人にとって、もはや一種のメンタルケアやマインドフルネスに近い役割を果たしていると言えるでしょう。
4K/8K時代の紀行番組を牽引する、本シリーズの映像革新
技術的な側面から見れば、本作はNHKが持つ最新の映像技術を「最も純粋な形」で出力する実験場でもあります。ノルウェー編第2回で披露されたドローン映像や、高精細な氷の接写は、テレビ受像機の進化を再確認させるための最高級のデモンストレーションとなっています。
今後、放送波がさらに高精細化していく中で、紀行番組の役割は「観光地を案内すること」から「その場の空気(空気感)を転送すること」へとシフトしていくはずです。本シリーズは、まさにその先駆けです。解像度が高まれば高まるほど、演出としてのテロップや過度なナレーションは邪魔なノイズになります。本作が示す「映像にすべてを語らせる」という潔い姿勢は、次世代のテレビ番組制作における一つの完成形(ゴール)を示唆していると言っても過言ではありません。
次はどの「最果て」へ?視聴者が待ち望む次なるレールの先
ノルウェー・NSB鉄道が私たちに見せてくれたのは、厳しい自然の中にこそ宿る、人間の知恵と鉄道の気高さでした。ボードーという終着駅に列車が滑り込んだとき、私たちの心には深い充足感と、それ以上に「もっと先へ」という渇望が残ります。
このシリーズの可能性は無限大です。次は南米のパタゴニアか、中東の砂漠を貫く一本道か、あるいは未踏の地アフリカの深部か。世界中に張り巡らされた鉄路がある限り、この「10分間の旅」に終わりはありません。テレビ界が「派手さ」を求めて迷走する中で、本作のように「ただ、そこにある風景」を愚直に切り取り続ける番組は、今後ますます希少な財産となっていくでしょう。私たちはこれからも、土曜の夜に10分間だけ現実を離れ、テレビという名の窓から「最果て」を夢見続けるのです。