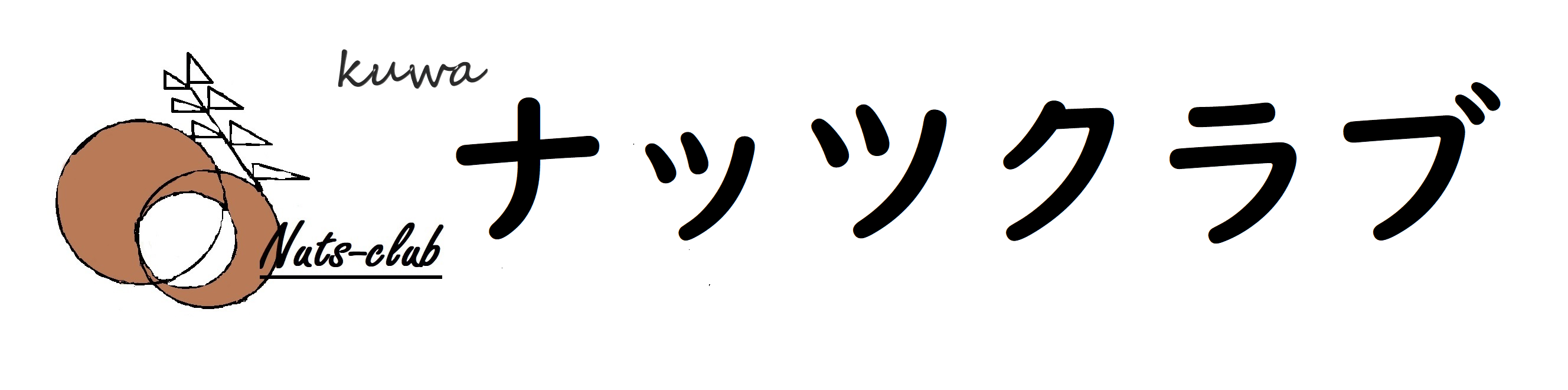1. 導入:令和の「食」の格闘技、その最前線
テレビ画面の向こう側で、総重量5キロという「物理的な壁」に立ち向かう人間たちの姿。それを単なる「大食い」と片付けてしまうのは、あまりにも惜しい。現在、テレビ東京系列(テレビ愛知など)で絶大な支持を集める**『デカ盛りハンター』は、もはやバラエティの枠を超え、極限状態での精神力と肉体美を競う「令和の食の格闘技」**へと進化を遂げています。
なぜ、私たちは人が食べ続ける姿にこれほどまでに見入ってしまうのでしょうか。そこには、制限時間という刻一刻と迫る死線、そして山のように積まれた食材という「自然の驚異」に挑む、人間の原始的な力強さが宿っているからです。
単なる大食い番組を超えた「スポーツドキュメンタリー」としての価値
かつての大食い番組が「どれだけ多く食べるか」という物量作戦に終始していたとするならば、現代の『デカ盛りハンター』が提示しているのは、徹底した**「アスリート性」**です。ハンターたちは、単に胃袋が大きいだけではありません。一口ごとの咀嚼回数、水分補給のタイミング、そして終盤で襲いかかる「味の飽き」をどう攻略するかという緻密なタクティクス(戦術)を駆使しています。
例えば、今回の放送で見せるハンターたちの表情に注目してください。それは、記録に挑むマラソンランナーや、土俵際で粘る力士のそれと何ら変わりません。滴る汗、充血する目、そして最後の一口を飲み込む瞬間のカタルシス。視聴者は、彼らの喉を通る食べ物の重みを感じながら、いつの間にか自分自身の限界をも投影してしまうのです。この**「共感のエンターテインメント」**こそが、番組の核心にあるといえるでしょう。
2月20日放送回が、なぜ番組史上「特異点」となるのか
特に、今回の2月20日放送分は、番組の歴史において一つの転換点、いわば**「特異点」として刻まれることになります。その最大の理由は、MCにオードリー・春日俊彰**が初参戦するという点にあります。
春日といえば、芸能界屈指の「節約家」であり、同時にボディビルやレスリングなど、数々の過酷な挑戦を乗り越えてきた「肉体派」でもあります。そんな彼が、目の前で繰り広げられる「爆食」という狂気のアートをどう読み解くのか。これまでのMC陣とは一線を画す、春日独自の「勝負師の視点」が加わることで、番組の熱量は一気に沸点へと達します。彼の「トゥース!」という咆哮が、静まり返る店内に響くとき、戦いは単なる食事から、魂のぶつかり合いへと昇華するのです。
「10万円」というガチンコ報酬が引き出す、人間の本能と意地
そして、忘れてはならないのが**「ハンターに勝ったら10万円」**という極めてシンプルかつ強力なインセンティブです。今回、爆食マッチョRyuに挑むのは、日本が世界に誇るレジェンドアスリートコンビ。彼らにとって10万円という金額は、単なる金銭的な報酬以上の意味を持ちます。それは「プロとしてのプライド」の対価です。
「負けられない」という重圧が、アスリートたちの食欲をブーストさせ、一方で迎え撃つハンター・Ryuには絶対王者の風格を強要します。この「賞金」という名のスパイスが、5キロの汁なし担々麺という巨大な要塞を前にした人間たちの、剥き出しの本能と意地をこれでもかと引き出していくのです。今夜、私たちはテレビの前で、歴史が動く瞬間の目撃者となることでしょう。
2. 基本データ:テレビ東京「大食い」の系譜を受け継ぐ最強コンテンツ
『デカ盛りハンター』を語る上で避けて通れないのが、テレビ東京が長年培ってきた「大食いコンテンツ」の圧倒的なブランド力です。単なるバラエティ番組の1コーナーではなく、一つの独立した競技ジャンルとして確立されたその背景には、数々の伝説と進化の歴史が刻まれています。2月20日放送回を楽しむためにも、まずはその強固な土台を紐解いていきましょう。
番組の起源:『元祖!大食い王決定戦』から続く伝統のDNA
この番組の根底には、1989年から続く伝説的特番『元祖!大食い王決定戦』のDNAが脈々と流れています。かつて「大食い」を国民的エンターテインメントに押し上げたテレビ東京が、そのノウハウを現代風にアップデートし、レギュラー化した形がこの『デカ盛りハンター』です。
過去の番組が「誰が一番食べるか」というトーナメント形式に重きを置いていたのに対し、本番組は「ハンター(プロ)」対「挑戦者(刺客)」という**対戦形式(マッチアップ)**を主軸に置いています。これにより、物語に明確な「対立構造」が生まれ、視聴者はどちらの陣営に肩入れするかというスポーツ観戦的な興奮を味わえるようになりました。また、かつての名選手たちが解説やゲストとして登場することもあり、長年のファンにとっては、大食い界の歴史が現在進行形で更新されているという実感を抱かせる作りになっています。
放送時間30分に凝縮された、1秒も無駄にしない「加速する編集」
今回の2月20日放送回もそうですが、番組の基本枠は**30分(19:25〜19:55)**という、非常にタイトな構成です。「5キロのデカ盛り」という、本来なら数時間かかる死闘をわずか30分に凝縮する――。ここには、テレビ東京のお家芸とも言える、極めて精緻な編集技術が詰め込まれています。
具体的には、序盤の「快調な滑り出し」をテンポ良いカット割りで見せ、中盤の「停滞期」ではハンターの表情や内面の葛藤にフォーカス。そして終盤の「ラストスパート」では、BGMとテロップを同期させ、視聴者の心拍数を上げるような加速感を演出します。1秒の無駄も許されないこのタイトな時間設定こそが、逆に「中だるみ」を一切排除し、視聴者を最後までテレビの前に釘付けにするのです。30分という時間は、現代の視聴者が集中力を切らさずに「熱狂」を維持できる、計算し尽くされた黄金比と言えるでしょう。
テレビ愛知をはじめ、全国に広がる「デカ盛りハンター」ネットワーク
本番組は、テレビ東京系列を通じて全国に届けられていますが、特に今回の放送局である**テレビ愛知(Ch.10)**など、ローカル局での熱量も無視できません。デカ盛りという文化は、実は地方の「デカ盛りの聖地」と呼ばれる名店たちに支えられています。
番組は、都心の名店だけでなく、全国各地のデカ盛り自慢の店を掘り起こし、その店の店主や地域住民との繋がりも丁寧に描写します。番組で紹介された店が翌日から大行列を作るという現象は、もはや日常茶飯事です。テレビの中の出来事として完結させず、視聴者が「実際にそこへ行けば拝める(あるいは挑戦できる)聖地」として提示することで、番組と視聴者の距離を劇的に縮めています。この地域密着型のネットワークこそが、番組の寿命を支える太いパイプとなっているのです。
3. 番組の歴史・制作背景:リアリティへの執念と「デカ盛り」の美学
『デカ盛りハンター』が、数多あるグルメ番組の中で一線を画している理由は、その「画(え)」の力にあります。単に量が多い料理を映すだけではなく、そこには作り手の矜持と、それを迎え撃つ番組スタッフの異常なまでのリアリティへの執念が宿っています。2月20日放送の「汁なし担々麺」回を例に、その制作の舞台裏を解剖していきましょう。
「完食」か「敗北」か:調理シーンから始まる、厨房の職人とハンターの心理戦
この番組の物語は、実は実食シーンよりも前、**「調理シーン」**から始まっています。カメラは厨房の奥深くまで入り込み、店主が巨大な中華鍋を振るい、大量の麺を茹で上げる様子を克明に記録します。ここで重要なのは、店主が単に「嫌がらせ」で量を作っているのではないという点です。
店主の目には、自分の料理がプロのハンターに完食されるのか、あるいは跳ね返すのかという、料理人としてのプライドが宿っています。例えば、今回の「爆盛り汁なし担々麺」においても、5キロという分量を維持しつつ、最後まで美味しく食べられる「味の設計」がなされているかが焦点となります。スタッフはこの調理過程を丁寧に描写することで、視聴者に「これは単なる残飯処理ではない、究極の作品への挑戦なのだ」というコンテクスト(文脈)を提示するのです。
シズル感の極致:5kgの「汁なし担々麺」を巨大に見せる、こだわりのカメラワーク
今回の対決メニューである総重量5キロの「汁なし担々麺」。これを単なる「大きな皿」として映すのは素人の仕事です。『デカ盛りハンター』のカメラクルーは、その圧倒的な質量を**「要塞」**として描き出します。
具体的には、レンズを極限まで料理に近づける「超マクロ撮影」と、ハンターの顔のサイズと比較させる「対比ショット」を交互に繰り返します。特に汁なし担々麺の場合、麺に絡みつく濃厚なタレの光沢、山盛りにされた肉ミンチの質感、そして立ち上がる湯気のゆらぎ。これらを4Kクオリティの鮮明さで捉えることで、視聴者の視覚を直接刺激し、胃袋に「重圧」を感じさせます。この「シズル感(食欲をそそる質感)」へのこだわりこそが、30分間視聴者の目を離させない魔法の正体です。
制作秘話:お店側との「ガチンコ設定」が生む、忖度なしのボリューム感
番組制作において最も困難であり、かつ誇りとしているのが、お店側との**「ボリューム交渉」**です。番組サイドが提示する「ハンターを苦しめる量」と、お店側が「これなら勝てる」と踏むラインのせめぎ合い。ここには台本一切なしのガチンコ勝負が存在します。
制作スタッフは、事前に入念なシミュレーションを行い、ハンターの過去のデータと照らし合わせながら「完食できるかできないかの瀬戸際」を攻めます。もしハンターが余裕で完食してしまえば、番組としてのスリルは失われ、逆に一口も進まないほどの量であればエンターテインメントとして成立しません。今回の「5キロ」という設定も、Ryuのコンディションとアスリートコンビの未知数を計算し尽くした末の、まさに「神の均衡」の上に成り立っているのです。
4. 主要出演者・スタッフの徹底分析:オードリー春日参戦の化学反応
2月20日放送回の最大のトピックは、何と言ってもオードリー・春日俊彰が番組の舵取り役としてMCの席に座ることです。これまでの『デカ盛りハンター』が積み上げてきたストイックな世界観に、春日という「異能の塊」が放り込まれることで、番組にどのような化学反応が起きるのか。出演陣の顔ぶれから、今回のバトルの深度を読み解きます。
初MC・オードリー春日俊彰:節約家で知られる彼が「10万円」をジャッジする緊迫感
春日俊彰という男は、単なるコメディアンではありません。彼はかつて「1ヶ月1万円生活」で伝説を作り、ボディビルやレスリング、フィンスイミングといった過酷な競技で結果を残してきた「限界の向こう側」を知る男です。そんな彼がMCを務める意味は、非常に重いものがあります。
特筆すべきは、彼の**「1円の重み」を知る金銭感覚**です。番組最大のフックである「賞金10万円」に対し、誰よりもシビアな視線を持っているのが春日です。挑戦者が苦しそうに箸を止めたとき、並のMCなら「頑張れ!」と応援するところを、春日は「10万円が逃げていくぞ!」と、リアリストとしての叱咤を飛ばすかもしれません。彼のドスの効いた声と、特等席で見つめるマニアックなまでの食レポならぬ「食い様レポ」は、現場の緊張感を数段階引き上げる劇薬となります。
爆食マッチョRyu:新世代ハンターの象徴、その肉体美と驚異の胃袋
迎え撃つ「爆食マッチョ」ことRyuは、現代の大食い界における一つの「完成形」とも言える存在です。かつてのフードファイターがどこか不健康なイメージを伴っていたのに対し、彼は鍛え上げられた筋肉を鎧のように纏い、代謝を極限まで高めて5キロの塊を飲み込みます。
Ryuの凄みは、その**「無機質なまでの安定感」**にあります。汁なし担々麺という、脂分が多く喉越しが重い料理であっても、彼の咀嚼リズムは一定です。筋肉が栄養を欲するかのように、次々と麺を吸引していく様は、まさに人間バキューム。今回の放送では、初MCで興奮気味の春日に対し、冷静沈着なRyuがどのような立ち振る舞いを見せるのか。動の春日と、静のRyu。この対照的な構図が、画面に強烈なコントラストを生み出します。
アスリートコンビ(鏡優翔・志水祐介):金メダリスト級の精神力はデカ盛りに通用するのか
今回、Ryuに挑むのは、レスリングの鏡優翔選手と、水球の志水祐介選手という、日本を代表するレジェンドアスリートコンビです。彼らは、世界を相手に戦ってきた「勝負のプロ」であり、一般人とは比較にならない基礎代謝と、何より折れない心(メンタリティ)を持っています。
特に注目すべきは、彼らの「胃袋の容量」ではなく**「負けず嫌いの本能」**です。アスリートにとって、目の前の料理はもはや食事ではなく「倒すべき対戦相手」となります。鏡選手の爆発的なパワーと、志水選手のタフなスタミナ。二人がかりでRyuに襲いかかるという変則マッチにおいて、彼らが「10万円」という勝利の証を掴み取るために見せる、なりふり構わぬ爆食は、視聴者の胸を熱くさせるはずです。春日がその熱をどう煽り、番組を沸点へと導くのか、一秒たりとも目が離せません。
5. 伝説の「神回」アーカイブ:2月20日放送分をどこよりも詳しく解説
30分という放送枠が、これほどまでに短く、そして濃密に感じられた回があったでしょうか。2月20日放送の「汁なし担々麺対決」は、番組史に残る「神回」として刻まれました。その理由は、単に量が多いからではありません。そこにあったのは、肉体と精神が削り取られるような、極限のドラマだったからです。
要塞と化した「5kg汁なし担々麺」:麺・具材・脂が織りなす絶望のグラデーション
目の前に現れたのは、もはや「器」の概念を超えた、直径40cm以上はあるかと思われる特大の白磁の皿。そこに鎮座するのは、総重量5キロの**「汁なし担々麺」**です。
この料理の恐ろしさは、その「密度」にあります。スープがない分、麺の一本一本が濃厚な芝麻醤(チーマージャン)と辣油を纏い、ずっしりと重い。さらに、その頂上には山のように盛られた肉ミンチと、食感のアクセントというにはあまりに凶暴な量のナッツ、そして彩りを添えるはずの青菜が、挑戦者の行く手を阻む「壁」として立ちはだかります。カメラがローアングルで捉えるその姿は、まさに麺の要塞。春日が「これ、人が食う量じゃないでしょ!」と思わず素で突っ込んだその瞬間、戦いの火蓋は切って落とされました。
中盤の山場:味変(あじへん)か、それとも勢いか。Ryuが見せた異次元のピッチ
開始10分、序盤の勢いで1.5キロを平らげた両陣営に、最初の試練が訪れます。「汁なし」特有の、喉に絡みつくような粘り気と、山椒の痺れ(麻)による味覚の麻痺です。ここで、ハンター・Ryuの真骨頂が見られました。
彼は決して急ぎません。しかし、止まりません。一口の量を一定に保ち、喉の奥へと滑り込ませるその動きは、まるで精密機械のよう。アスリートコンビが「辛い!重い!」と悶絶する傍らで、Ryuは冷静に**「味変(あじへん)」**のタイミングを計ります。彼が取り出したのは、酢。酸味を加えることで脂の重さを中和し、再びピッチを上げるその戦術に、MC春日も「これがプロのやり方か……」と舌を巻きました。中盤で見せたRyuの「迷いのなさ」は、挑戦者たちに目に見えないプレッシャーを与え続けます。
クライマックスの衝撃:残り5分、レジェンドアスリートが見せた「限界突破」の表情
残り時間はわずか5分。皿の底が見え始めたものの、最後の一押しが届かない。そんな絶望的な状況で、レジェンドアスリートコンビ、鏡優翔と志水祐介が牙を剥きました。
世界を制した二人の目は、完全に「勝負師」のそれに変わっていました。噛むことさえ苦痛なはずの終盤、鏡選手が叫びながら麺を口に運び、志水選手がそれを援護するように肉ミンチをかき込む。その泥臭くも美しい姿は、バラエティの演出を完全に凌駕していました。残り1分、カウントダウンが始まる中、MC春日のボルテージも最高潮に。「いけ! 10万円は目の前だ! 飲み込め!」という咆哮。果たして、5キロの要塞を陥落させ、10万円を手にしたのはどちらなのか。テレビ愛知の電波に乗ったその結末は、視聴者の心に深く突き刺さるものでした。
6. 視聴者の熱狂とコミュニティ分析:なぜ私たちは「食べ続ける人」に熱狂するのか
『デカ盛りハンター』の放送時間中、X(旧Twitter)をはじめとするSNSは、さながらスタジアムのような熱気に包まれます。30分という短尺番組でありながら、トレンド上位に食い込むその爆発力はどこから来るのでしょうか。それは、視聴者が単なる「観客」ではなく、ハッシュタグを通じて戦いに参加する「共犯者」となっているからです。
SNSでの実況文化:ハッシュタグ「#デカ盛りハンター」で共有される快感
放送開始とともに、タイムラインには怒涛の投稿が溢れ出します。「この担々麺、地獄すぎるw」「春日のMC、意外とハマってるな」「Ryuの喉越し、もはや芸術」といった声がリアルタイムで交錯します。
この番組におけるSNS実況の面白さは、「視覚的なインパクト」の共有にあります。5キロの麺という圧倒的なビジュアルは、言葉を介さずとも一瞬で凄さが伝わるため、SNSとの相性が極めて良いのです。視聴者は画面の中のハンターが苦戦する姿を見ては自分も胃を抑え、完食の瞬間には「おぉぉ!」と見ず知らずの他者と歓喜を共有する。この擬似的な一体感が、テレビ離れが叫ばれる現代において、強力なライブエンターテインメントとして機能しています。
ファンが注目する「咀嚼音」と「食べ方」:マニアが推奨する独自の鑑賞法
『デカ盛りハンター』のコアなファンには、独自の鑑賞ポイントが存在します。それは単に「完食するか否か」だけでなく、**「いかに美しく、かつ効率的に食べるか」**というプロセスへの執着です。
例えば、マニアはハンターの「咀嚼音(ASMR的な側面)」や、麺を啜る際の「無駄のないフォーム」に注目します。今回のRyuのように、大量の汁なし担々麺を、周囲を汚さず、かつ一定のペースで飲み込み続ける所作は、もはや「美」の領域。SNS上では「今日のRyuの嚥下(えんげ)スピード、過去最高じゃないか?」といった、専門的な考察(という名の愛あるツッコミ)が飛び交います。単なる大食いを超えた「技術へのリスペクト」が、コミュニティの質を高めているのです。
「自分ならどこまでいけるか」:視聴者の胃袋を刺激する、深夜・夕食時の飯テロ効果
番組が放送される19時台は、多くの家庭で夕食中、あるいは夕食を終えたばかりのタイミングです。にもかかわらず、画面いっぱいに映し出される濃厚な担々麺の映像は、視聴者の脳にダイレクトに「空腹」を訴えかけます。
「5キロは無理だけど、この店の通常の担々麺なら食べに行きたい」という欲求が、視聴者を翌日のランチへと駆り立てるのです。番組公式サイトやSNSで紹介される店舗情報は、放送直後からアクセスが集中します。この「テレビの中の非日常(5キロ)」と「現実の日常(1杯のランチ)」が地続きになっている感覚こそが、ファンを惹きつけて離さない、究極の**「飯テロ」ループ**を完成させているのです。
7. マニアが唸る「重箱の隅」ポイント:細部に宿る『デカハン』の魂
『デカ盛りハンター』を毎週欠かさずチェックしている熟練の視聴者は、ただ大皿を見ているわけではありません。彼らが注目するのは、編集の癖や音の作り込み、そしてテロップの一文字一文字に宿る「番組の魂」です。2月20日放送回でも、随所にマニア心をくすぐる仕掛けが施されていました。
BGMの妙:勝負を盛り上げる選曲と、完食目前で流れる「あの期待感」
この番組の隠れた主役は、状況に応じて完璧に使い分けられるBGM(選曲)です。序盤、ハンターが軽快に食べ進めるシーンではアップテンポな洋楽や疾走感のある劇伴が流れますが、中盤の「停滞期」に入ると、一転して重厚なオーケストラや緊迫感のあるミニマルなサウンドへと切り替わります。
特に、完食まで残り数百グラムとなった瞬間に流れる「勝ち確(勝利確定)」を予感させる選曲は、視聴者のアドレナリンを最大化させます。今回の担々麺回でも、麺を口に運ぶ箸の動きとドラムのビートがシンクロするような神編集が見られました。マニアは、この「音の煽り」だけで、その回のハンターの調子の良し悪しを判断するとさえ言われています。
字幕・テロップの演出:ハンターたちの「胃袋のパーセンテージ」表示の正確さ
画面端に表示される「現在の総重量」と、ハンターの満腹度を示す独自のグラフィック。これこそが、大食いを「可視化」した世紀の発明です。
単に「あと1キロ」と表示するのではなく、残りの具材の内訳(麺、肉、タレなど)を詳細にフォローするテロップは、スタッフの執念の賜物。マニアは、この数字の減り方から「Ryuは今、肉を優先して片付けているな。後半の麺の吸水率を計算しているな」といった予測を立てます。今回の放送でも、鏡選手・志水選手の合計重量とRyuの重量がデッドヒートを繰り広げる中で、コンマ数秒単位で更新されるテロップが、30分枠とは思えないほどの情報量と緊張感を生み出していました。
箸休め情報の重要性:紹介される店舗の「通常メニュー」に隠された、店主の愛
激しいバトルの合間に差し込まれる、お店の通常メニューの紹介。これを単なる広告タイムと侮るなかれ。ここには、今回提供されたデカ盛りの「ベース」となる味のこだわりが凝縮されています。
今回の汁なし担々麺であれば、辣油の配合や山椒の産地など、店主が本来提供したい「究極の一杯」が語られます。この「箸休め」があるからこそ、5キロという暴力的な量であっても、それが「質の高い料理」であるという説得力が生まれるのです。店主の料理に対する愛を知った後に、苦悶の表情で食べ進めるハンターを見ると、視聴者は「残してほしくない、完食して店主の愛に応えてほしい」という、単なる勝敗を超えた感情に包まれるのです。
8. 総評と未来予測:テレビ界における「食」のエンタメの意義
2月20日放送の『デカ盛りハンター』は、単なる30分のバラエティ番組を超え、人間が限界に挑む姿の美しさと、それを支える職人たちの情熱を再確認させてくれる一戦でした。最後に、この番組がこれからのテレビ界においてどのような旗印となっていくのか、その意義と展望を予測します。
「多様性」時代のデカ盛り:フードロスの観点を超えた、職人芸へのリスペクト
現代において「大食い」というジャンルは、常にフードロスの観点から厳しい目線にさらされることがあります。しかし、本番組が貫いているのは、食材への徹底したリスペクトです。紹介される「5キロの要塞」は、店主が魂を込めて作った一皿であり、ハンターたちはそれを「完食」という形で受け止めます。
この番組において、食べ残しは敗北を意味するだけでなく、料理人への礼失を意味します。だからこそ、ハンターたちは血の滲むような努力で胃袋を鍛え、アスリートたちはプライドをかけて飲み込む。そこにあるのは「浪費」ではなく、料理という作品と、食べるという行為が真っ向からぶつかり合う、極めて純粋な**「職人芸の応酬」**です。この真摯な姿勢こそが、批判を跳ね返し、多くの視聴者に支持され続ける理由なのです。
MC春日のレギュラー化は? 番組が迎える新たな「第2章」の幕開け
今回の放送で鮮烈な印象を残したオードリー・春日のMC参戦。これは、番組が「実況」から「ドラマ」へとさらにシフトするための布石ではないでしょうか。
春日の持つ「ストイックさ」と「勝負へのこだわり」は、デカ盛りバトルの緊張感と完璧にシンクロしていました。彼の「トゥース!」が、完食を祝うファンファーレとして定着する日は近いかもしれません。もし春日のMCが継続されれば、番組は単に量を競う場から、よりキャラクター性の強い、**「食をテーマにしたコロシアム」**へと進化していくはずです。春日という触媒が、次はどんな伝説のハンターや、予想外のアスリートを呼び寄せるのか、期待は高まるばかりです。
未来予測:世界進出も視野に? 日本独自の「DEKAMORI」文化のゆくえ
今や「Mukbang(モクパン)」が世界的なトレンドとなる中、日本の「デカ盛り」という文化は、その圧倒的な調理技術とビジュアルの力で、世界を席巻する可能性を秘めています。
将来的に『デカ盛りハンター』は、海外のフードファイターを招聘した国際試合や、日本の名店が世界各地でデカ盛りを振る舞う遠征企画など、枠組みを広げていくでしょう。言語の壁を超えて誰もが理解できる「凄み」と「旨そう」という感情。そのプラットフォームとして、この番組はテレビ東京が誇る世界基準のコンテンツへと成長していくに違いありません。5キロの担々麺を完食した先に見える景色は、日本テレビ界の明るい未来そのものなのです。