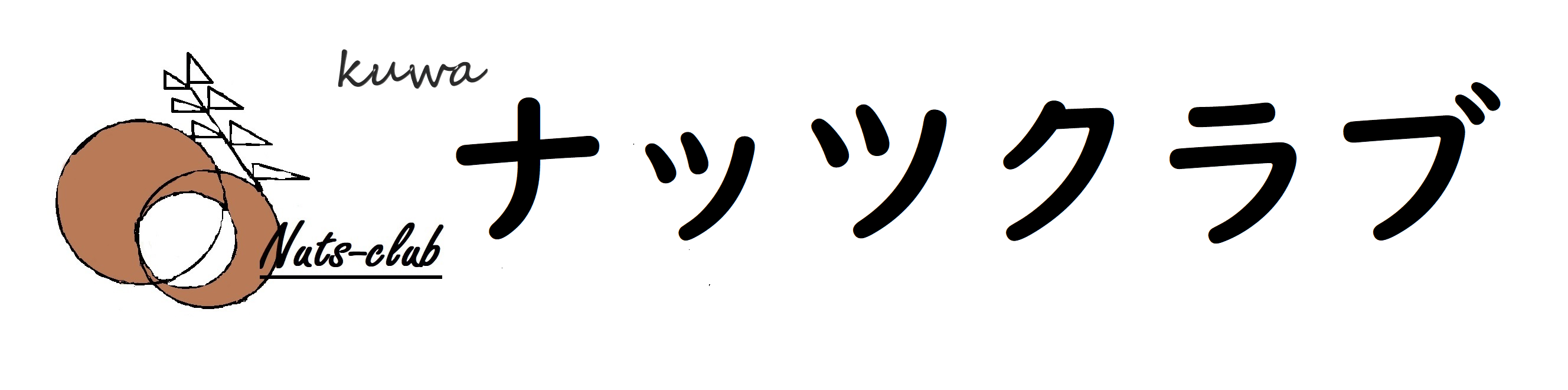1. 導入:龍馬の「眼差し」を現代に残した男の物語
私たちが教科書やドラマで目にする坂本龍馬。懐手に寄りかかり、遠くを見据えるあのあまりにも有名なポートレート。もし、江戸時代末期に「ある男」が命を懸けて技術を磨いていなければ、私たちは龍馬の顔すら知らなかったかもしれません。
その男の名は、上野彦馬。長崎が生んだ日本最初期のカメラマンであり、同時に狂気的なまでの情熱を秘めた科学者でもありました。2026年2月17日放送の『先人たちの底力 知恵泉』では、この稀代の先駆者が、いかにして「見えないはずの未来」を写し取ったのかに迫ります。
現代の私たちはスマホで一日に何枚もの写真を撮りますが、彦馬にとっての写真は、化学反応との死闘であり、時代の魂を定着させる神聖な儀式でした。番組のゲスト、デザイナーの篠原ともえさんと戦場カメラマンの渡部陽一さんが、それぞれの視点から彦馬の「信念」を解剖していきます。
2. 放送概要:夜10時にタイムスリップする45分間
放送は2月17日(火)の午後10時から10時45分。NHK Eテレが贈る「知恵泉」は、歴史上の人物が直面した困難をどう乗り越えたかを探る、ビジネスパーソンやクリエイターにとっても宝の山のような番組です。
今回の放送は「選」として、過去の名作回を再構成したもの。しかし、上野彦馬の物語は古びるどころか、情報過多の現代において「真の価値を記録する」とはどういうことかを改めて問いかけてきます。長崎の風を感じるような45分間、視聴者は幕末の動乱期へと誘われることでしょう。
3. 上野彦馬の執念:化学から挑んだ「写真術」の独学
彦馬の凄さは、単に「写真を撮った」ことではありません。当時はカメラも薬品も輸入に頼るしかなく、極めて高価で不安定なものでした。そこで彼は、「ないなら作ればいい」という、現代のメーカー精神の原点ともいえる行動に出ます。
そのエピソードは強烈です。写真の現像に必要なアンモニアを得るために、彼は肉付きの牛の骨を地面に埋め、わざと腐らせてそこから成分を抽出しようとしました。当然、凄まじい悪臭が漂い、近隣住民からは「あそこでは恐ろしい人体実験が行われている」と疑われ、奉行所に通報される始末。
しかし彦馬は怯みません。彼は単なるカメラマンではなく、日本初の化学テキスト『舎密局必携(せいみきょくひっけい)』を著した科学者でもありました。驚くべきは、自ら苦労して開発した技術を独占せず、惜しげもなく出版して広めたことです。「新しい技術は多くの人が使うことで、初めて社会の役に立つ」という彼の思想は、現代のオープンソースの精神にも通じています。
4. 幕末のアイコン誕生:上野撮影局に集った志士たち
長崎の中島川沿いに開かれた「上野撮影局」。そこには、新しい日本を夢見る若者たちが吸い寄せられるように集まりました。
当時の写真は「湿板(しっぱん)写真」と呼ばれ、感光板が乾かないうちに撮影と現像を終える必要がありました。さらに露出時間は数分に及ぶことも。龍馬が台に肘をついているのは、単にカッコつけているだけでなく、体が動かないように固定するための支えでもあったのです。
彦馬のレンズは、志士たちの「覚悟」を逃しませんでした。死を覚悟して戦場へ向かう高杉晋作の、冷徹なまでに研ぎ澄まされた眼差し。それらを記録できたのは、彦馬自身が薬品の臭いにまみれ、爆発の危険と隣り合わせで戦う「現場の人間」だったからに他なりません。
5. 日本初の従軍カメラマン:西南戦争で見せたプロの流儀
明治10年、日本最後の内戦「西南戦争」が勃発します。彦馬はこの戦いに、日本初の従軍カメラマンとして身を投じます。しかし、彼が撮った写真は、私たちが想像する戦場写真とは少し趣が異なります。
番組内で渡部陽一さんが深く踏み込むであろうポイントが、彦馬の「死者の姿を撮らない」という姿勢です。凄惨な戦場において、彼は命を落とした兵士たちの姿を直接的にレンズに収めることはありませんでした。代わりに彼が写したのは、主のいない陣地や、破壊された風景、そして生き残った者たちの静かな表情でした。
そこには、レンズを向ける対象への深い敬意と、写真という新技術を「見世物」にしないという強固な倫理観がありました。記録者としての義務と、人間としての情愛。その葛藤の末に辿り着いた彦馬のまなざしは、現代の報道のあり方にも鋭い問いを投げかけます。
6. SNSの反響:歴史ファンとカメラ女子が熱視線を送る理由
放送中、SNS(特にX)では「彦馬、凄すぎる」「牛の骨を埋めるところから始めるDIYの極致」といった驚きの声が溢れます。特に、自分の専門外の分野に独学で挑むその姿勢は、キャリア形成に悩む現代の若者たちに深く刺さっています。
また、戦場カメラマン・渡部陽一さんの「あの独特の間」と、鋭い本質を突くコメントも人気の理由です。彼が彦馬の写真を評する時、そこには同じ戦場を歩いた者にしかわからない共鳴が生まれます。
視聴者の間では「今度長崎に行ったら、上野撮影局の跡地を巡りたい」といった聖地巡礼の動きも活発です。不便だったからこそ、一枚の写真に込められた「祈り」の深さが、今のデジタル世代には新鮮に映るのでしょう。
7. マニアの視点:彦馬の「写真」に隠された構図と意図
さらにマニアックに踏み込むなら、彦馬のライティング(採光)に注目です。彼が長崎に建てたスタジオは、北側に大きな窓を配し、安定した柔らかい光を取り込む工夫がなされていました。
彦馬の写真が150年以上経った今見ても美しいのは、彼が「光の性質」を完全にコントロールしていた科学者だったからです。また、彼の写真は周辺部がわずかに暗くなる「周辺光量落ち」が見られますが、それが逆に中央に座る人物の存在感を際立たせる効果を生んでいます。
番組ではおそらく触れられない細部ですが、彼が使っていたレンズの特性や、当時彼が好んだ背景幕の質感まで観察すると、彦馬という男がいかに「空間全体」をプロデュースしていたかがわかります。
8. まとめと今後の期待:新技術に信念を込めるということ
『知恵泉』が描き出した上野彦馬の姿は、単なる「昔のカメラマン」ではありませんでした。それは、未知の技術に立ち向かう「勇気」と、それを社会のために役立てる「無私」の精神、そして対象への「愛」を併せ持った、真のイノベーターの姿でした。
上野彦馬の知恵、それは「答えがないなら、土を掘ってでも見つけ出せ」という執念です。そして「手に入れた技術は、他人のために使え」という高潔さです。
私たちが手にするスマートフォンのカメラ。そのレンズの奥には、かつて腐った牛の骨の臭いに耐えながら、光の正体を追い求めた一人の男の情熱が、今も静かに息づいています。